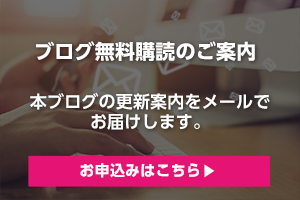今や、3人に1人が転職する時代です。
特に若年層の離職率が高く、厚生労働省が発表した「新規学卒者の離職状況」のレポートによると、大卒入社3年以内の離職率は30%を超えています。
【出典】新規学卒者の離職状況,厚生労働省
『従業員の離職率を下げる』ことが、すでに経営課題となっている企業もあれば、今後課題となってくる企業もあるかと思います。
そんな企業の人事担当者・経営者の方向けに、こちらの記事では、人材の流出を防ぐ手法の一つでもある「社内転職制度」について徹底的に解説します。
社内転職制度のメリットや導入リスク、設計のポイントや適切な運用方法など、多くの方が気になるポイントをまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。社内転職制度とは

社内転職制度とは、同じ企業内で部署や職種の変更ができる制度のことです。
従業員に、新しいキャリア形成や自己実現の場を提供するとともに、企業には、優秀な人材の流出を防ぎ、社内のノウハウ共有を促進できる利点があります。
社内転職制度には、大きく分けて2種類あります。
1つ目は、企業側が、新規事業や人材不足の部署の求人募集を行い、希望する従業員は手を挙げて選考を受けることができる「社内公募制度」。
2つ目は、従業員が自ら異動を希望する部署に、直接異動のアピールができる「社内FA制度(フリーエージェント制度)」。
どちらも同じ企業内で従業員が別部署に異動する制度のことを指します。
社内転職制度を利用する企業側のメリット
ここからは、社内転職制度を利用する企業側のメリットについて解説します。
優秀な人材が定着し、離職を防ぐ
社内転職制度では、従業員に対して転職を必要とせずに新しいキャリア形成の場を提供することができます。
また、企業で働きながらも「異なる業種を経験したい」「新しいスキルを身につけたい」と日々考える優秀な人材にとっては、仕事へのモチベーション向上にもつながります。
企業内で職種やキャリアの選択肢が増えることで、結果として、従業員の外部への転職を防ぎ、優秀な人材を企業に定着させることができます。
採用コストを削減できる
離職する従業員が多いと、新たに外部から人材を確保するための求人広告費やエージェント利用料、採用活動のための実働時間が必要となり、採用コストがかかります。
しかし、社内転職制度を利用することで優秀な人材が定着し、外部への流出を防ぐことができるため、採用コストの削減につながります。
企業の生産性・組織の柔軟性が向上する
社内転職制度により、従業員が別部署・別職種で経験やスキルを積むことで、企業全体にもノウハウが蓄積されていきます。
また、部署をまたいだ人材の異動が流動的になることで、蓄積されたノウハウが共有されていき、新規事業の立ち上げなど企業のイノベーション創出につながる可能性も生まれます。
社内転職制度を利用することで、組織の柔軟性が向上し、従業員のモチベーションやスキルが上がることで、企業全体の生産性も上がるというメリットがあります。
社内転職制度を利用する従業員側のメリット
次に、社内転職制度を利用する従業員側のメリットについて解説します。
ミスマッチが起こりにくい
社内転職制度は、通常の転職とは異なり、事前に異動先の部署の雰囲気や業務の実態を把握できます。
また、社外への転職ではないため、企業文化や理念、働き方にも一定の理解があり、部署異動を行った後も適応しやすいのが特徴です。
従業員は、希望する部署の実態や業務を把握しやすく、企業側は、これまでの経験や従業員の適性を考慮した異動が可能なため、ミスマッチが起こりにくいというメリットがあります。
キャリアの選択肢が増える
社内転職制度を利用することで、従業員は自身のスキルや興味関心に合わせて、希望する部署や職種に挑戦できます。
これまでは、外部への転職でしか叶わなかった「スキルアップ」や「経験の積み重ね」を企業内で実現できることで、キャリアの選択肢を増やすことができます。
社内転職制度を導入するリスクと対策について

ここからは、導入リスクと対策について解説します。
社内転職制度は、起こりうるリスクを事前に把握しきちんと対策を行うことで適切に運用することができますので、一つずつ確認していきましょう。
人員のバランスが崩れるリスク
社内転職制度を導入すると、人員のバランスが崩れる可能性があります。
たとえば、特定の部署に従業員が集中し、他部署の従業員が不足してしまうという事態などが考えられます。
従業員を適切に配置することができなければ、結果として、組織全体のバランスが崩れることにつながってしまうこともあります。
社内転職制度を導入する場合は、組織全体の人材のバランスを考慮した上で、従業員の異動をコントロールする必要があるでしょう。
<対策>
- 組織全体のバランスを考慮した上で公募する
- 従業員が適切に配置されるよう採用計画と連携する
- 異動の多い部署の問題点を洗い出し、改善する
業務効率が低下するリスク
社内転職制度を導入することで、業務効率が低下するリスクもあります。
従業員が部署異動をするということは、業務の引き継ぎをしっかりと行わなければなりません。
しかし、異動先の部署で引き継ぎがうまくいかない場合や、異動元の後任が不在の場合、業務に支障が出ることもあります。
社内転職制度を導入する際は、業務の引き継ぎや後任者の育成を事前にしておきましょう。
<対策>
- 引き継ぎを円滑にするために、業務の可視化・マニュアル化を進めておく
- 急な異動は避け、制度設計時に「引き継ぎ期間」を設けておく
- 後任者を育成する「メンター制度」や「OJT制度」を整備する
社内の人間関係に影響が出るリスク
社内転職制度では、従業員同士の人間関係に影響が出る可能性もあります。
たとえば、「あの従業員が社内転職する」ということを上司や同僚に知られてしまったため、異動を妨げられたり、裏切り行為だと責められたりといった事態が生じることもあります。
従業員のモチベーション向上と成長の機会となる良い制度にもかかわらず、異動前に人間関係で気まずい思いをしてしまうと、制度の意味がありません。
社内転職制度を導入する際は、上司や同僚の制度への理解を促し、異動しやすい環境を整えておくことが大切です。
<対策>
- 社内転職制度の事前周知及び上司や関係部署の理解を深めておく
- 異動が不利益でないことを明示し、業務に支障を出さない制度設計を行う
- 従業員のプライバシーの保護を徹底し、応募や採用前段階では外部に漏らさない
社内転職制度を導入している企業の事例3選
こちらでは、社内転職制度を実際に導入している企業の事例をご紹介します。
自社に導入をお考えの企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。
富士通株式会社「ポスティング制度」
「ポスティング制度」とは、富士通グループ内の空きポジションが常時公開され、従業員のキャリア開発に応じて自ら応募・挑戦ができる制度のことです。
2020年に導入後、2022年までの3年間で応募した従業員は約2万人、そのうち7500人が希望するポジションに異動しました。
異動の応募にあたって上司への事前申告は必須ではありませんが、面談であらかじめキャリアの希望について上司と意思疎通を図っておくことを推奨しています。
上記のポスティング制度と、別組織・別部署に短期間だけ異動できる「Jobチャレ!!」制度を併用することで、従業員は自身のキャリア形成に向き合えます。
「ポスティング制度」の課題と解決策
課題①:異動先での職務内容と従業員とのミスマッチ
解決策:情報の透明化、実直なコミュニケーションの徹底
基本的に、社内転職制度を利用した従業員と異動先とのミスマッチは起こりにくいものの、ごく稀に、想定していたものとは異なる仕事を任されてしまい、異動した従業員のモチベーションが下がってしまうという課題があります。
富士通株式会社でも同様に、異動後に従業員から「話が違う」という声が上がりました。
そのため、富士通株式会社では、応募者には面接時に「異動先の部署でやりたいこと」を具体的に伝えるように促すとともに、求人を出す部署側にも「職場の実態」を誇張せずに説明するよう徹底しています。
課題②:異動による人員バランスが崩れる
解決策:部署の上司に対して「価値」や「魅力」の発信を促す
社内転職制度では、人気の部署に異動が集中し、異動人員の格差が生じるという課題もあります。
富士通株式会社には、不人気な部署のトップが「うちは地味だから」「不人気だから」と悲観的になり、異動希望を集める対策をせず最初から諦めてしまうという課題がありました。
そのため、ポスティング制度で公募が集まらない部署に対して、「職場の価値や魅力を伝えること」を積極的にするよう促しました。
【参考】より良い生き方・働き方を自ら考え舵を握るキャリアオーナーシップ,富士通株式会社
ソニー株式会社「キャリアチャレンジ(社内公募)制度」
「キャリアチャレンジ(社内公募)制度」とは、ソニー社内の各部署から公募が出され、キャリア形成に意欲的な従業員は誰でも自発的に応募・異動できる制度です。
ソニー株式会社は、社内求人募集による公募制度を1966年から導入しており、制度開始以後の異動者は累計で8000人を超えています。
年に2回(2月・8月)行われており、毎年一定数の従業員が制度を利用しています。
異動に際し上司の許可は不要、異動先チームリーダーとの1on1ミーティングといった機会を設けるなど、異動後のサポートが充実しています。
「キャリアチェンジ(社内公募)制度」の課題と解決策
課題 :既存の社内公募では個人のキャリア形成に限界
解決策:今の時代に沿った異動システムの導入及び環境整備
1966年から社内公募制度を運用しているソニーですが、従来の社内公募制度では“今の”従業員のキャリア形成に対する考え方と齟齬が生まれてしまい、社内調査の結果、社内公募制度の利用に対する従業員の関心が低下していることが明らかになりました。
そこで、「FA制度」「キャリアプラス制度」「キャリア登録制度」という異動システムを新たに導入します。
「FA 制度」とは、社内で数年にわたり仕事のパフォーマンスで高評価を取り続ける従業員を対象に、受入希望する部署が本人に対してオファーを出して、従業員自身に異動を決定してもらう制度です。
社内公募制度よりも、より個人が意思決定できる環境を整えた制度です。
*FA制度では毎年約200~300人にFA権利が付与されており、行使するのは2割程度です
「キャリアプラス制度」は、兼務やプロジェクト型募集としての異動制度です。従業員は、現在の配属先での業務を維持しつつ、2~3割程度の時間を新たな職務に投じることができる制度です。
完全に他部署に異動する必要はないため、兼業しながらスキルアップやキャリア形成ができます。
*キャリアプラス制度では、導入後2年半で約60件程度のマッチングが成立しています。
「キャリア登録制度」は、求人先ありきの社内公募とは対照的に、異動を希望する従業員自らが社内に求職者として登録し、公募している部署に共有される制度です。
受入希望する部署が従業員に興味を持った場合は面接を実施し、マッチングが成立すると異動となります。
*キャリア登録制度では、登録した従業員の2~3割が異動しています。
既存の社内公募制度と並行して、新たな異動システムを運用することで、今まで以上に「個」を中心とした従業員のキャリア形成を支援しています。
ファイザー株式会社「ジョブポスティング制度」
「ジョブポスティング制度」とは、ファイザーの日本法人・海外法人関係なく、すべてのポジションに誰でも応募することができる制度です。
ファイザーでは1992年から社内公募制度を導入し、2013年からは社長のポジションも含め、マネジャー以上のポジションはすべて社内公募制となりました。
2015年度には500 件ほどの公募件数があり、日本法人の従業員5,000人弱に対して応募件数は1,400件近くに上りました。
応募の段階で異動元上司への報告は必要なく、異動決定後は上司に拒否権もありません。
また、部署ごとに業務内容を説明してくれるアンバサダーと呼ばれるメンバーを配置し、興味があればアンバサダーから説明を聞いて、異動を希望する部署の業務のイメージを事前につかむこともできます。
「ジョブポスティング制度」の課題と解決策
課題 :従業員のキャリア形成に対する主体性の欠如
解決策:1on1ミーティングを随時実施+キャリア形成に関する新しい考え方の導入
当初ファイザーでは、ジョブポスティング制度の一環として、上司と部下でキャリア形成に関する面談を年に2回、決まったタイミングで実施していました。
しかし、上司主体のもと面談が行われていたため、従業員のキャリア形成に対する主体性が失われるという課題が浮上します。
課題を解決するため、キャリア形成に関する1on1ミーティングを部下から上司に依頼する形で随時実施する仕組みへと変更し、部下が主体的にジョブポスティング制度を利用してキャリア形成できるよう、「ジグザグ成長キャリアパス」という考え方を新たに導入しました。
『同じ部門内・事業領域でスキルの習得や経験を積むための水平異動』『キャリアチェンジを考える従業員向けに部門をまたいだ異動』『同じ部門内・事業領域で上位ポジションに就くための垂直異動』といった“ジグザグ”のキャリア形成を支援することで、従業員の潜在能力を引き出しています。
社内転職制度を適切に運用するポイント
ここまで、社内転職制度のメリットや導入リスクと対策、社内転職制度を活用している企業の事例を紹介しました。
では、実際に自社で社内転職制度を導入・運用していくためにはどうすれば良いでしょうか。
こちらでは、社内転職制度を適切に運用していく上で押さえておきたいポイントについて解説します。
以下の4つのポイントを意識して、適切に社内転職制度を運用することで、従業員と企業の双方にとって価値のある仕組みとなるでしょう。
事前に選考基準と制度規定を固めておく
社内転職制度を適切に運用するためには、事前に選考基準や制度の規定を固めておくことが重要です。
異動可能な部署の求める人材やスキル、選考基準を明確にした上で応募要項を作成すること、従業員の応募条件を定めておくこと、そして、公募から採用・異動までの流れを設計しておくことなどが挙げられます。
運用する側・応募する側の混乱を避けるためにも、制度の透明化や公平性の確保に注意しながら、制度の規定を固めていきましょう。
社内転職しやすい環境を整えておく
社内転職制度の適切な運用のために、環境整備も大切です。
制度内容を事前に従業員に周知させること、上司や関係部署の理解を得ること、異動元上司に拒否権を行使させないこと、異動に対してポジティブな文化を形成すること、トライアル期間などを設けてミスマッチを防ぐ仕組みを確立させること、そして、社内転職前後の従業員に対するサポートやアフターケア対策を準備しておくことが必要です。
異動を希望するすべての従業員が積極的に社内転職制度に挑戦できるよう、事前に企業内の環境を整えておきましょう。
従業員のプライバシーを守る
適切な社内転職制度の運用のためにも、従業員のプライバシー保護は徹底する必要があります。
従業員の誰が・どこの部署に異動をしたくて社内転職制度を利用しているのかはもちろんのこと、社内転職制度への応募理由や選考状況、異動の可否といった情報が他の従業員に漏れる可能性が少しでもあると、従業員は安心して制度を利用することができません。
また、上記の情報が外部に知られてしまうことで、部署内や企業内での人間関係に影響が出てしまったり、制度を利用した従業員本人のパフォーマンスが下がったりすることもあります。
従業員が社内転職制度を利用しやすい環境構築のためにも、プライバシーの保護を徹底し、制度への信頼を高めることが適切な運用への近道です。
評価制度と連動してモチベーションを高める
社内転職制度を、単なる部署異動や職種変更のための手段としてではなく、従業員のキャリア形成の一環として位置付けることで、適切な運用につながります。
そのためにも、社内転職制度による新たなスキルの習得や成果を、従業員の昇進や昇給に反映するというルールを明確にして、異動後の人事評価制度を整えておくことが大切です。
「社内転職制度を利用して新しい部署で成果を出すことが、年収アップや出世につながるかも」という可能性を提示することで、従業員のモチベーションアップにもつながります。
社内転職制度を成功させるなら人事評価を効率的・効果的に
社内転職制度を適切に運用する上で人事評価を正しく行うことが大切ですが、人事評価業務はシートの管理や集計表作成など手間と時間がかかるため、企業・従業員ともに納得のいく人事評価ができていない場合も多いのではないでしょうか。
「人事評価の業務・作業の対応に追われている」
「他部署と連携が取れておらず進捗管理が滞っている」
「今の人事評価システムが使いづらくて社員から不評」
そんな企業の人事担当者・経営者の方には、「人事評価システムP-TH/P-TH+(ピース/ピースプラス)」がおすすめです。
「P-TH/P-TH+」は既存のExcel評価シートをそのままシステム化することができ、あらゆる職種に対応する人事評価システムです。
面倒なファイル管理も無くなり、進捗管理もリアルタイムで確認できることもポイントです。
また、人事評価シートの内容も変更できるため、社内転職制度による異動で評価項目に変更があった場合も反映することができます。
蓄積された人事評価データを分析することもできるので、人事評価制度をスムーズに社内転職制度と連携させることができるでしょう。
人事評価システム P-TH/P-TH+ | AJS ソリューション・サービスサイト Solution Navigator
まとめ
社内転職制度は、優秀な人材の流出を防ぎ、社内のノウハウ共有を促進させるメリットがあります。
また、従業員のキャリア形成にもつながるため、働くモチベーションアップにもつながります。
導入前には制度設計をきちんと行い、従業員と企業の双方が気持ちよく社内転職制度を活用できるよう心がけましょう。
<< コラム監修 >>
株式会社サクセスボード 萱野 聡
日本通運株式会社、SAPジャパンで採用・教育を中心とした人事業務全般に幅広く従事。人事コンサルタントとして独立後、採用コンサルタント、研修講師、キャリア・アドバイザーとして活躍中。 米国CCE Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー、産業カウンセラー。
- カテゴリ:
- 人材活用
- キーワード:
- 人材活用






 << コラム監修 >>
<< コラム監修 >>