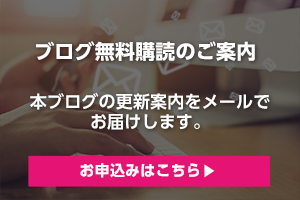日本企業ではかつて、職務や勤務地を後から決める「メンバーシップ型雇用」が主流でした。しかし、近年のグローバル化に伴い、欧米で主流の職務(ジョブ)に適した人材を採用する「ジョブ型雇用」を導入する企業が増えています。この記事では、雇用制度の見直しを考えている企業担当者や経営者に向けて、メンバーシップ型雇用の特徴やジョブ型雇用との違い、メリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

メンバーシップ型雇用とは?
現在ではさまざまな雇用形態が存在していますが、日本企業では長らくメンバーシップ型が基本とされてきました。いまでもその仕組みを基礎とする企業は多く、その特徴やジョブ型雇用との違いを理解することで、あらためてそのメリットや課題が見えてきます。まずは、メンバーシップ型雇用がどのような雇用形態なのかを解説します。
メンバーシップ型雇用の特徴
メンバーシップ型雇用とは、日本独自の働き方であり、新卒採用時に業務内容や勤務地を限定せず、総合職として雇用契約を締結する仕組みのことです。高度経済成長期に、多くの人材を必要とした企業が一括採用・長期的な人材育成を進めたことで普及し、「日本型雇用」とも呼ばれています。
メンバーシップ型は終身雇用が基本であり、新卒採用者を長期的に育成します。また、人に職務を割り当てるスタイルのため、業務内容や勤務地が変更になることもめずらしくありません。また、賃金は長期雇用を前提とした年功序列型で、勤続年数や年齢が重視される傾向があります。職務が違っても、同じ役職であれば基本給に大きな差がつきにくい一方、職能給や企業の評価制度によっては、総支給額や年収に違いが生じる場合があります。
メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の違い
メンバーシップ型雇用とよく比較されるのが、欧米流の雇用システムであるジョブ型雇用です。ジョブ型雇用は、特定の仕事を遂行するために従業員を募集・採用するのが特徴です。働き方もジョブ型の場合、業務内容や勤務地が細かく決められており、原則として契約外の異動や転勤は発生しません。賃金も本人のスキルや仕事の成果によって変動します。このように、ジョブ型の働き方では、メンバーシップ型のように幅広い知識を持って多くの業務に対応できるゼネラリストよりも、特定の業務を遂行できるスペシャリストが求められます。
メンバーシップ型雇用のメリット
メンバーシップ型には、企業にとっての以下のメリットがあります。
新卒一括採用でコストを抑えられる
メンバーシップ型では、大勢の新卒就職者に対して会社説明会や面接を行い、一括採用するため、採用活動の効率化が可能です。計画的に人材を確保できるため、個別に求人を出す中途採用と比べて採用コストを抑えやすいというメリットもあります。さらに、企業文化や価値観に合った人材を育成しやすく、長期的な戦力として活躍が期待できます。
柔軟な人材配置が可能になる
メンバーシップ型雇用では、柔軟な人材配置が可能なこともメリットのひとつです。業務内容や勤務地を限定していないため、社員の異動や転勤、職務変更ができ、異動や転勤を通じてゼネラリストを育成できます。
愛社精神が強い人材を育てやすい
終身雇用が基本のメンバーシップ型では長く働くことで、組織への信頼感や愛着が生まれ、「組織の一員である」という愛社精神の強い従業員を育てやすいこともメリットに挙げられます。愛社精神の強い従業員が増えれば、離職率の低下やチームワーク、モチベーション、生産性の向上などにつながります。
メンバーシップ型雇用のデメリット
多くの日本企業で用いられているメンバーシップ型ですが、企業には一般的に以下のデメリットが挙げられます。
スペシャリストが育ちにくい傾向がある
メンバーシップ型雇用では、あらゆる業務に精通したゼネラリストが育ちやすい一方、特定の分野で専門的なスキルを有したスペシャリストが育ちにくい傾向があります。得意な業務に集中しにくく、専門性の低下や機会損失につながる可能性があります。
人件費が増える場合がある
メンバーシップ型の賃金は、勤続年数や年齢を重視した年功序列型です。そのため、勤続年数が長い従業員が増えるほど、会社が支払う人件費も必然的に増加します。さらに、終身雇用制度のもとでは、経営が一時的に悪化してもスキルの低い従業員を簡単に解雇できず、上昇し続ける賃金を支払い続ける必要があります。
従業員のモチベーションや生産性を維持しにくい場合がある
年功序列が前提のメンバーシップ型は、スキルを磨いて成果を上げても年齢が若く、勤続年数が短いうちは昇給につながりにくいです。このような不公平感は若手従業員を中心に、仕事に対するモチベーションを低下させ、生産性の停滞や離職率の向上を招くおそれがあります。
メンバーシップ型雇用の課題
時代の変化に伴って、メンバーシップ型の働き方に対して「多様な働き方」「同一労働同一賃金」といった点で課題が指摘されています。このような課題を解決することは、さらに働きやすい職場づくりにつながり、企業を成長させるうえで重要な役割を果たします。
働き方の多様化に対応しづらい
近年、コロナ禍の影響や働き方改革の推進により、企業における働き方が多様化しています。しかし、メンバーシップ型では、会社から与えられた業務に責任をもって積極的に関わることができる人が評価されるため、仕事と子育てや介護、病気などを両立したい従業員にとっては負担が大きくなります。評価されることが難しく、テレワークや短時間勤務といった柔軟な働き方も評価されにくい傾向があります。そのため、これまでの制度だけでなく、社風や職場の文化を見直し、多様な働き方を受け入れやすい環境を整えることが求められます。
同一労働同一賃金への対応が必要になる
メンバーシップ型雇用は、同一労働同一賃金への対応が難しいという課題もあります。同一労働同一賃金とは、同じ仕事をする従業員に対して同一の賃金を支払うという考え方のことです。しかし、メンバーシップ型では年功序列型賃金のため、同じ労働でも勤続年数や年齢が違えば、支払う賃金の額が異なります。そのため、同一労働同一賃金を実現させるためには、給与体系の見直しが必要です。
同一労働同一賃金ガイドライン案における給与および賞与、福利厚生の待遇差について
メンバーシップ型雇用であっても適切な評価が重要
戦後の高度経済成長期を支えたメンバーシップ型雇用ですが、年功序列によって成果がきちんと評価されず、なかなか昇給しない給与体系は、仕事へのモチベーションを維持しにくく、不平不満を募らせる若手従業員も少なくありません。また、ライフステージの変化を理由に一度キャリアを中断してしまうと、スムーズに昇給・昇進しにくくなるのもメンバーシップ型雇用のデメリットです。
このような従業員の不満を解消するためには、メンバーシップ型雇用のデメリットや課題を理解したうえで、自社に合った人事評価制度を構築することが重要です。特に、従業員の仕事に対するパフォーマンスやスキルを適切に評価し、評価が給与や待遇などに反映される人事評価制度を構築すれば、従業員も納得しやすく、モチベーションやエンゲージメントの向上にもつながります。
人事評価制度のシステム化なら「P-TH/P-TH+」
人事評価制度の見直しを行うなら、あらゆる企業に適用できる「P-TH/P-TH+」がおすすめです。「P-TH/P-TH+」なら今まで使用していたExcelの評価シートをそのままシステム化できます。面倒なファイル管理の必要もなく、評価シートの集計など人事評価業務にかかる作業時間を大幅に短縮し、業務の効率化を実現します。また、従業員の情報を一元管理できるので、人材データベースとして人材マネジメントに活用でき、育成計画の策定や適切な配置にも役立ちます。
人事評価システム P-TH/P-TH+ | AJS ソリューション・サービスサイト Solution Navigator
まとめ
メンバーシップ型雇用は、日本企業で長らく採用されてきた働き方で、終身雇用や年功序列を基本としています。メリットとして、新卒一括採用による効率化や柔軟な人材配置が挙げられる一方、スペシャリストの育成が難しく、働き方の多様化に対応しづらい、同一労働同一賃金への対応が必要といった課題もあります。近年、ジョブ型雇用に切り替える企業も増えていますが、両者の比較を通じて、自社に合った評価制度や雇用システムを構築することが重要です。
<< コラム監修 >>
株式会社サクセスボード 萱野 聡
日本通運株式会社、SAPジャパンで採用・教育を中心とした人事業務全般に幅広く従事。人事コンサルタントとして独立後、採用コンサルタント、研修講師、キャリア・アドバイザーとして活躍中。 米国CCE Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー、産業カウンセラー。
- カテゴリ:
- 人事部門向け






 << コラム監修 >>
<< コラム監修 >>