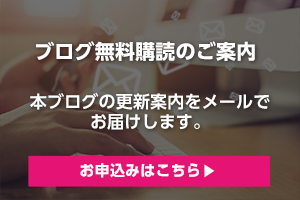社員の育成やマネジメントに必要不可欠な、「人事評価制度」。
適正な人事評価を行うことで、人材育成のみならず、組織全体の業績の向上にもつながります。
「人事評価制度を導入したいけど、どうすればいいの?」
「企業でうまく人事評価制度を運用するポイントは?」
「人事評価制度のこと、もっと詳しく知りたい!」
そこで、こちらの記事では、人事評価制度の目的や手法、制度の運用を円滑にするためのポイントについて徹底的に解説していきます。
企業の生産性を上げたい経営者の方や、人事評価制度の導入を検討している人事担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
人事評価制度とは?
人事評価制度とは、社員の業績や行動、能力などを適正に評価し、その評価に基づいて社員の報酬や昇進といった処遇を決定する仕組みのこと。
社員一人ひとりの貢献度合いを正しく評価することで、人材の定着やモチベーションアップにつながり、企業全体の生産性向上にも結びつきます。
人事評価における主な評価項目は、「業績評価(成果・実績)」「能力評価(知識・スキル)」「情意評価(仕事への姿勢・態度)」の3つ。
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| 業績評価 | 一定の評価期間に『社員・部門単位の業績・目標の達成度』を評価する方法。 主に、社員個人や部門全体が、どれだけ会社に貢献したかを売上や利益といった数値で測ります。 |
| 能力評価 | 業務を遂行するうえで必要な『知識やスキル』を評価する方法。 等級や職種によって評価基準を設定し、成果や業績ではなく、業務上での経験や社内研修で得られた能力を総合的に見て評価します。 |
| 情意評価 | 仕事に取り組む姿勢や態度、意欲を評価する方法。 社員一人ひとりの働き方や、仕事への向き合い方、社内での接し方などを定性的に見極めます。 |
人事評価制度は、社員一人ひとりの能力や成果を客観的に把握して、適切に評価する必要があることから、評価項目や設定された目標に照らしあわせて、絶対評価により行うのが一般的です。
しかし、数値化された評価基準のみで人事評価をしてしまうと、組織の信頼関係や企業の文化形成に影響が出てしまうこともあるため、結果だけでなく過程にも注目すると良いでしょう。
人事評価制度の導入目的について

人事評価制度ですが、そもそもなぜ企業に導入する必要があるのでしょうか。
こちらでは、人事評価制度を導入する目的について解説します。
企業の理念や経営方針の共有
人事評価制度には、企業の理念や経営方針、会社の求める社員像が反映されるため、組織文化や価値観の浸透にも寄与します。
単なるスキルや実績の評価だけではなく、「企業理念やビジョンと合致しているか」「会社の求める人物像に近い行動を取っているか」といった評価項目を入れることで、社員一人ひとりが企業理念を理解し、自らの行動で体現できるようになります。
目標設定と生産性の向上
人事評価制度では、社員あるいは部門単位で明確な目標を設定する必要があります。
目標を設定することで、社員・部門単位で「何をするべきか」が明確になるとともに、企業理念や経営方針への理解が深まり、組織としての方向性にも一貫性が生まれます。
また、明確な目標設定は、業務の優先順位付けの指標となり、社員一人ひとりの自発的な行動を促すこともできます。
そして、人事評価制度では、設定した目標に対する社員の行動や部門ごとの成果を、定期的に評価してフィードバックを行います。
習慣的に振り返ることでそれぞれの強みや課題が明確になり、改善を重ねることで、個人だけでなく企業全体の生産性向上にもつながります。
人材配置の最適化・処遇の公平性の担保
人事評価制度によって、社員一人ひとりの能力や特性を見極めることができるため、その評価に基づいて適切な部署・役職に配置できます。
また、明文化された人事評価に応じてあらかじめ処遇を決定できるため、公平性も担保されます。
個々の能力を適正に評価して、最適な人材配置・公平な処遇を与えることで、企業全体の組織力・生産力が上がります。
社員の人材育成
人事評価制度は、社員一人ひとりの能力や業績を可視化することができるため、人材の育成や組織のマネジメントにも活用できます。
そもそも、人事評価制度には、「社員を評価して終わり」ではなく「社員の可能性を引き出す」という目的もあります。
明瞭な評価制度があることで、社員のスキルや成果に基づいた研修制度やスキルアップ制度の策定・実施といった人材育成の指針にもなります。
人事担当者や上司が、社員や部下の強み・弱みを把握して、業務の調整や新しい挑戦の機会を提供することで、一人ひとりの自発的な行動や成長につながり、組織も強くなっていくでしょう。
社員のモチベーション向上
人事評価制度は、社員のモチベーションの向上にもつながります。
制度の導入によって、評価基準や処遇が明文化されることで、社員が感じる不公平感を解消することができます。
そして、適切な人事評価は、社員と企業の信頼関係を深め、社員一人ひとりの成長意欲や貢献意欲をより高めてくれます。
日々の努力や成果が公平に評価されることで、「もっと頑張ろう」「次はこうしてみよう」と社員のやる気も高まり、結果として組織全体の活力や成果に反映されるでしょう。
人材の評価に必要な3つの制度
社員を評価するときは、主に「等級制度」「評価制度」「報酬制度」の3要素が必要とされており、人事評価制度はそのうちのひとつです。
実際に、人事評価制度を導入する前に、社員の評価に必要な3つの制度について確認していきましょう。
等級制度
等級制度とは、社員を『職務・役割・能力』に応じて分類し、序列化する制度のこと。
組織の中で、社員をどう位置付けるかという人事評価制度における土台の制度ともいえます。
等級制度は、「職能資格等級制度(メンバーシップ型)」「職務等級制度(ジョブ型)」「役割等級制度(ミッショングレード型)」の3つに分類されます。
| 等級制度 | 内容 |
|---|---|
| 職能資格等級(メンバーシップ型) | 社員の職務遂行能力に応じて等級を決める人事評価制度。 日本の人事制度の代表格で、勤続年数が長いほど職能が高くなりやすい傾向があります。 年功序列や長期雇用を前提とした評価制度です。 |
| 職務等級(ジョブ型) | 職務に応じて等級を決める人事評価制度。 欧米を中心に海外で広く導入されている人事制度であり、職務内容や責任の重大性によって等級を設定します。 |
| 役割等級(ミッショングレード型) | 社員の役割に応じて等級を決める人事評価制度。 『社員に期待していること』に基づいて等級を設定するため、納得感が生まれやすいです。 |
大手企業をはじめとする日本企業の多くは、職能資格等級制度を採用してきましたが、近年の働き方改革や成果主義の高まりから、職務等級制度とのハイブリッドで設計する企業も増えてきました。
また、組織の多様化により、人事制度に対する柔軟性や納得感が求められる時代となった現代では、役割等級制度に移行する企業も増えています。
評価制度
評価制度とは、社員の業績や行動・能力を正しく評価する制度のこと。
「業績評価」「能力評価」「情意評価」といった評価項目から、社員一人ひとりを定量的・定性的に評価し、等級や報酬といった処遇に反映されます。
報酬制度
報酬制度とは、評価や等級に応じて、給与・賞与・手当などの報酬を決定する制度のこと。
社員の評価や役割に見合う報酬を正当に支払うことで、社員のモチベーション向上につながります。
評価制度とうまく連動させることで、「社員の成長の方向性」を明確にし、組織全体の生産力を高めることができます。
人事評価制度の手法について

実際に人事評価制度を導入するにあたり、どの評価方法が自社にあっているのかを検討する必要があります。
ここからは、人事評価制度の中でも代表的な手法について解説していますので、一つずつ確認していきましょう。
MBO(目標管理制度)
MBO(Management by Objectives)とは、『社員個人または部署・部門ごとのグループ単位で目標を設定し、その達成度合いによって評価する』制度のこと。
アメリカの経営学者ピーター・ドラッカー氏が提唱したマネジメント概念であり、彼の著作である『マネジメント』でも詳しく述べられています。
社員自身で目標を設定し、目標達成に向けて行動に集中することができるため、社員一人ひとりの主体性や責任感を引き出すことができます。
また、目標は部署メンバーや上司と部下の間で共有し、定期的な進捗確認とフィードバックを行うため、人材育成やチームとしての一体感にも寄与します。
MBOでは、半年〜1年という期間の中で、達成可能な目標を定量的・定性的に設定するため評価もしやすく、評価に対する処遇への納得感も高いのが特徴です。
※OKRについて
OKR(Objectives and Key Results)とは、企業やチーム全体の目標(Objectives)と、その達成度を測るための具体的な指標(Key Results)を設定し、進捗を管理する目標管理手法の一つ。
※ 社員の挑戦を促すための手法の一つであり、人事評価制度ではありません。
MBOと似ていますが、より難易度の高いチャレンジングな目標を掲げ、1〜3ヶ月ごとに達成度合いを評価するため、組織の成長スピードを加速させる効果が期待できます。
OKRを導入することで、企業全体の目標に対する社員の理解が深まり、チームで一体感を持って業務に取り組むことが可能となります。
360度評価
360度評価とは、『社員一人を、上司や部下、同僚、他部署の人など、立場の異なる複数の視点から評価する』制度のこと。
一方向のみでは把握しきれなかった社員の能力や働く姿勢などを、多方面から評価することができるようになります。
しかし、評価者の主観や人間関係が評価に影響を与える可能性もあるため、評価基準はきちんと明文化し、評価者に対しては評価者研修などを事前に行うとよいでしょう。
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは、『高い成果・業績・パフォーマンスを出す社員に共通する「行動特性(Competency)」を基準に、社員の行動を評価する』制度のこと。
たとえば、営業職に従事する社員のコンピテンシーは、相手のニーズを引き出すヒアリング力や粘り強さ、信頼を構築するスキルなど。
企業ごとに、実際に貢献している社員の行動やスキルを分析してコンピテンシーを設定するため、組織にあった人材像を明確化できます。
また、『自分に何が足りないのか』『何を求められているのか』を社員は把握しやすくなるため、人材育成という点においても有効です。
バリュー評価
バリュー評価とは、『企業が定めた理念や行動規範に対し、社員がどれだけ理解して実践できたかを評価する』制度のこと。
仕事の成果だけでなく、「仕事に対してどう向き合っているのか」「成果を出すまでにどんな行動をしたのか」という日頃の活動や成果に至るまでの過程も評価する考え方です。
企業が大切にする行動指針や価値観を、社員の行動に落とし込んで評価するため、普段の行動にまで企業理念を浸透させることができるのもポイントです。
人事評価制度を導入する手順について
ここからは、人事評価制度を導入するための手順についてお伝えします。
実際に導入を検討している経営者の方や人事担当者の方は、参考にしてみてください。
現状の課題を分析する
人事評価制度を導入するにあたり、今の組織や社員一人ひとりの抱える課題を分析することが大切です。
一人当たりの生産性は上がっているか、社員のモチベーションは低下していないか、人材育成はきちんと行われているかなど、定量的・定性的の両面から現状の課題を分析します。
具体的には、企業の売上や業績を同業他社と比較してデータを分析したり、社員アンケートを実施して個々の課題を洗い出したりすることから始めると良いでしょう。
組織や社員の課題を明確にすることで、人事評価制度の目的・目標を設定することができます。
※ 人事評価制度の目標とは、「処遇の公正化」や「人材育成」、「社員のモチベーション向上」「組織文化の浸透」など企業によって異なります。
評価項目・基準を策定する
人事評価制度の目的・目標を設定できたら、評価項目と評価基準を策定します。
職種や部門によって、評価項目・基準は異なるため、「何を評価するか(評価項目)」「どう評価するか(評価基準)」をそれぞれ決めます。
また、評価基準を策定するタイミングで、MBOや360度評価、コンピテンシー評価など、『どの評価手法を採用するか』を検討しておくと良いでしょう。
評価方法・処遇のルールを決定する
評価項目・基準の設定を終えたら、評価方法や、評価に基づいた処遇について決めます。
策定した評価項目を五段階で評価する、年に2回に分けて評価する、評価方法はMBO手法を採用するなど、評価ルールを具体化しておくと、円滑に人事評価制度を運用することができます。
また、給与・賞与・手当などの報酬や昇進など、評価に基づく処遇のルールを明確にすることで、制度の公平性が担保され、適切な評価へとつながります。
制度説明会・評価者研修を実施する
人事評価制度を設計したら、社員への周知を徹底します。
人事評価制度の目的や評価基準の趣旨、評価方法など、すべての社員に正しく理解してもらうためにも、人事評価制度を導入する前に説明会を実施することは必須です。
また、評価者に対しては、事前に評価者研修を実施することで、公正な評価をすることができます。
導入する前に企業全体に目的や意義を浸透させることで、人事評価制度に対する社員の納得感も生まれ、運用もスムーズに行えるでしょう。
人事評価制度の運用を成功させるポイント
こちらでは、人事評価制度の運用を成功させるポイントを解説します。
以下の4つのポイントをしっかり押さえて、人事評価制度をうまく運用していきましょう。
制度を明文化して社員に周知する
繰り返しとなりますが、人事評価制度の運用を成功させるためには、人事評価制度を明文化して社員にしっかりと周知させることが重要です。
「なぜこの制度を導入したのか」「制度では何を大切にするのか」「評価基準や項目はどう設定したのか」を社員一人ひとりに明確に伝えることが、成功への近道となります。
あいまいな評価項目や処遇ルールだと、かえって社員のモチベーション低下につながってしまうこともあります。
社員の育成や成長を促すための人事評価制度でもあるため、制度の公平性をきちんと伝えて、社員一人ひとりに納得感を持って行動してもらいましょう。
フィードバック文化を定着させる
人事評価制度は、社員一人ひとりの成長だけでなく、企業全体の生産性向上にもつながります。
一方的に評価結果を伝えて終わらせるのではなく、評価のフィードバックは定期的に行い、社員同士のコミュニケーションを増やしていくことが大切です。
フィードバックを定着させることで、細やかに評価内容や改善点を伝えることができ、社員一人ひとりの成長意欲も高まります。
また、フィードバック文化が広がることで、上司と部下、ひいては組織全体の信頼関係の構築にも寄与します。
定期的に評価項目・基準を見直す
企業経営の現場では、事業領域の拡大や業務プロセスの変更、社員数の増減など、さまざまな動きが日々発生します。
あらゆる変化に瞬時に対応できるよう、人事評価制度は定期的に見直すことがポイントです。
その際、評価項目や評価基準は『見える化(データ化)』しておくことが大切。
人事評価シートや評価基準表などのテンプレートを活用して、人事評価のデータを見える形にしておくことで、変化に応じた見直しを適切に行うことができます。
人事評価システムを活用する
人事評価制度を形骸化させず、継続的に運用するためには、人事評価システムの活用も効果的です。
紙やExcelベースでの人事評価管理は、使いやすくて加工しやすい反面、情報の非対称性や運用ミスが生じやすく、人事担当者をはじめ、評価に関わるすべての社員の負担が大きくなってしまいます。
さらに、人事評価をする人数が増えるほど管理は煩雑になり、情報漏洩のリスクも上がってしまいます。
人事評価制度を成功させるためには、制度を運用する環境を整えることが重要です。
また、人事評価システムを導入することで、評価業務の時間が短縮し、社員に丁寧なフィードバックを行うことができ、評価に対する社員の納得感も上がるというメリットもあります。
人事評価システムならP-TH/P-TH+
人事評価制度を適切に運用するなら、「人事評価システムP-TH/P-TH+(ピース/ピースプラス)」がおすすめ。
「P-TH/P-TH+」とは、既存のExcel人事評価シートと、人事評価制度をそのままシステム化することができる人事評価システムです。
煩雑になりがちな評価シートのファイル管理が無くなり、人事評価の進捗管理もリアルタイムで確認できるため、メールの誤送信や評価シートの紛失、期日までの評価漏れといった運用ミスや情報の非対称性も防ぐことができます。
また、人事評価シートの内容も変更できるため、社員の増減や評価項目の変更があった場合でも反映することができます。
蓄積された人事評価データを分析することもできるので、人事評価制度の定期的な見直し・改善にも適しています。
そして、2025年4月から『1on1機能』も標準装備されました。
定期的な1on1の実施によって、上司と部下の関係をより良いものに構築することができれば、人事評価制度の円滑な運用にもつながるでしょう。
まとめ
人事評価制度を導入することで、社員一人ひとりを適正に評価でき、人材育成や社員のモチベーションを上げることができます。
人事評価制度で大切なことは、評価の公平性を担保し、社員の納得感が生まれること。
社員の評価を通じて企業文化を形成し、個人の成長と組織の成長を結びつけることで、企業全体の生産性向上につなげていきましょう。
<< コラム監修 >>
株式会社サクセスボード 萱野 聡
日本通運株式会社、SAPジャパンで採用・教育を中心とした人事業務全般に幅広く従事。人事コンサルタントとして独立後、採用コンサルタント、研修講師、キャリア・アドバイザーとして活躍中。 米国CCE Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー、産業カウンセラー。
- カテゴリ:
- 評価制度
- キーワード:
- 評価制度






 << コラム監修 >>
<< コラム監修 >>