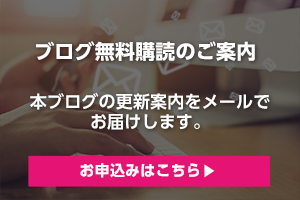社員の成果や能力を適正に評価するはずの人事評価も、評価者の認識の歪みや偏りによって、本来の公平さを損なうことで、「人事評価エラー」が発生する場合があります。
評価の誤りは、社員のモチベーション低下や離職、組織全体の生産性低下など、企業にさまざまな影響を及ぼすため、早急な是正・対策が必要です。
そこで、こちらの記事では、評価者が陥りやすい人事評価エラーの主な発生原因や、それによって引き起こされる問題、評価エラーを防ぐための対策について、わかりやすく解説します。
人事評価エラーとは
人事評価エラーとは、評価者が陥りやすい心理的な錯誤のことで、意図的または無意識のうちに心理や感情に影響されて公正な評価ができなくなる現象です。
性別や年齢、出身など、評価者のさまざまな要素に基づいたバイアス(偏見・先入観)が、人事評価に影響を与えてしまうケースがあります。
また、評価者本人が、評価制度や評価基準をきちんと理解していないと、人事評価エラーが起きる可能性も高まります。
人事評価エラーを放置してしまうと、被評価者だけでなく、企業全体にも悪影響を及ぼします。
しかし、多くの評価者・被評価者は、人事評価エラーに気付いていません。
人が人を評価するシステムである以上、主観、感情をまったくのゼロにするのは難しいのですが、評価者が日々意識をすることで、より公正な人事評価制度の運用が可能になります。
人事評価エラーが引き起こす問題
人事評価エラーが組織内で発生すると、以下のような問題を引き起こします。
- 社員のモチベーション低下
- 組織全体の生産性・効率の悪化
- 人事評価に対する信頼性の欠如
人事評価エラーによって、被評価者の努力や成果が正しく評価されないと、社員のやる気やエンゲージメントが下がります。
社員のモチベーション低下は勤労意欲や成長意欲に影響し、組織全体のパフォーマンスや業績の低下に直結します。
人事評価エラーが常態化してしまうと、人事評価そのものに対する社員の不信感が蓄積され、その結果、評価者である上司やチーム間の関係が悪化し、社員の離職増加につながる可能性があります。
人事評価エラーが発生する7つの原因

では、人事評価エラーはなぜ起こってしまうのか。
人事評価エラーに共通しているのは、「公平性」と「客観的事実の欠如」です。
ここからは、人事評価エラーの代表的な例と、それを引き起こす原因について見ていきましょう。
ハロー効果
ハロー効果は、心理学の世界で使われている用語で、認知バイアスとも呼ばれています。
たとえば、
「話し方が明るく人当たりがよい、だから大きなプロジェクトも安心して任せられる。」
「身だしなみが悪く洗練されていない、だから仕事にも不備が多いのだろう。」
といったように、特定の社員を評価するとき、目立ちやすい特徴に引っ張られて評価者による評価が歪められてしまう現象です。
評価者は、先入観を手放し、見た目や会話の印象に左右されないよう気をつけなければいけません。
評価項目1つにつき、具体的に1つの事実に限り、照らし合わせていく作業が有用です。
中心化傾向
中心化傾向とは、評価基準を中心に寄せて、当たり障りのない評価をしてしまう人事評価エラーです。
「自分の評価に自信がない」「優劣をつけることにより部下の反発を避けたい」など、評価者の保身から生まれるケースが多いのが特徴です。
中心化傾向に陥らないためにも、まずは、評価期間中に被評価者の情報を十分に集めることから始めましょう。
面談時に、無難に人事評価を済ませようとする心理を一度捨て去り、客観的に『良いものは良い』『悪いものは悪い』と、シンプルに判断するように訓練します。
寛大化・厳格化傾向
寛大化傾向は、評価が甘くなり、厳格化傾向は、評価が厳しくなる人事評価エラーです。
主な原因は、評価者が人事評価制度そのものを理解しておらず、好き嫌いや気分など、主観や感情に委ねた人事評価を、良しとしている点にあります。
自分の評価基準は、企業の評価基準と異なるという事実をしっかりと認識し、価値観そのものを見直す必要があります。
逆算化傾向
逆算化傾向とは、最終的な総合評価を決めてから、帳尻を合わせるように評価を調整してしまう人事評価エラーです。
評価者、企業側が賞与や業績賞与の支給額をある程度決めていて、相対評価を取り入れて調整するなどの例も含まれます。
逆算化傾向は、賞与や昇格のために最終評価だけを意識することで起こります。
対策は、被評価者自身が、各評価項目は今後業務を行う上での指標となることを認識することです。
期末誤差
本来、人事評価は評価期間の月日全てが対象となるものの、評価期間の後半あるいは面談の直前に起きた出来事などが全体の評価に大きく影響されてしまうことを、期末誤差といいます。
被評価者を評価する材料が少ないことが原因で、評価者は、期末に起きた「プロジェクトの成功・失敗」などの事象を中心に考えてしまいます。
対策として、評価期間の期初から期末にかけて事実に即した記録をつけて、発生時期によって人事評価に偏りが出ないようにすることです。
評価期間中に、『中間評価』のタイミングを設けることも効果的でしょう。
論理的誤差
論理的誤差とは、評価者の頭の中にある理屈・推論に基づいて評価を下す人事評価エラーです。
いくつかの評価要素を、評価者の都合のよい解釈でつなげたり、混合するなどしてしまうため、公平性に欠けたプロセスを辿っています。
たとえば、「自己啓発に率先して取り組んでいるから、業務知識はアップしているはず。」というように、被評価者の行動に勝手に理屈をつけて結論づけてしまうというのが論理的誤差です。
こうした評価エラーを回避するためには、人の思考にはクセがあると認識し、自分本位な理論で評価をしていないか、評価項目ごとに振り返ることが大切です。
対比誤差
対比誤差とは、評価者自身の持っている能力や資質を、無意識のうちに被評価者と対比してしまい、過大評価・過少評価してしまう人事評価エラーです。
たとえば、
「私(評価者)は語学が堪能で英語がネイティブ。しかし、被評価者は、留学経験がなく語学に関連する資格を所持していない。」
といった思考になると、「被評価者は自分に比べ劣っている」と判断し、評価者は、勝手に紐づけた項目の評価を下げてしまいます。
その逆もあり、評価者自身が苦手とする分野を得意とする被評価者に対して、自分と対比して高い評価をつけてしまうこともあります。
対策は、企業で定めた評価基準をよく理解し、推論はせず、常に評価基準に則った評価を行うことです。
人事評価エラーを減らす対策とは?
人が関わっている限り『人事評価エラーは誰もが陥るもの』と、評価者自身が認識することが対策のスタート地点です。
人事評価エラーのほとんどは、事実に基づいた客観的な観察と情報収集で防げます。
社員の意識や能力は目には見えません。
そのため、評価の期間中は、一定のリズムで観察を続け、行動や結果など事実に基づいた評価材料を収集し、記録して情報を積み重ねていくことがなによりも重要です。
人事評価における評価者の客観性と正確性を養うためには、定期的な評価者研修の開催と、チェック機構の設置が有効です。
また、アップデートし続ける評価基準を正しく理解できるよう評価者のレベルを底上げし、二段階チェック+αで制度を運用させることです。
ここからは、評価制度運用のスタート地点である「目標設定」と「プロセス」において、人事評価エラーを排除できる具体的な対策について解説します。
数値目標と行動目標を設定する
人事評価エラーを防ぐために、評価者と被評価者が、評価対象期間中の目標(数値目標・行動目標)を明確に設定します。
数値目標は、売上高、契約件数、コスト削減金額、業務効率化(時間・行程数)など、数値に換算できるものを設定します。
行動目標は、勤務態度や納期の順守など業務に取り組む姿勢を設定する目標です。
入社して間もない社員は、行動目標の比率を上げるなど、評価内容のバランスを調整すると良いでしょう。
目標を具体化する
人事評価エラーの対策として、設定した目標を具体化する必要があります。
数値目標は、「売上高○○万円、契約件数○○件」など、具体的な数値を目標に設定しますが、行動目標など数値化が難しい項目の場合は、事前に評価者は定められた評価基準を被評価者と共有します。
たとえば、「週1回のチームミーティングで必ず1回以上、改善提案など自分の意見を言う」や「新しい業務ソフトの操作習得のため、eラーニングを受講して社内テストに合格する」など、会議の議事録や受講修了証といったものを評価の指標にすると良いでしょう。
評価基準は、可能であれば4段階や6段階といった偶数に設定し、中心化傾向の人事評価エラーを発生させないように工夫すると良いでしょう。
具体化した目標は、チーム内で共有し、協力する姿勢や競い合う環境に活用していきます。
定期的に面談・評価を行う
人事評価制度を正しく運用させるためには、目標達成及び被評価者のモチベーション維持のために、定期的に1on1ミーティング・面談を開催したり、目標設定を見直したりすることが重要です。
社会情勢や被評価者の環境変化によって目標達成が明らかに難しい場合は、その時点で柔軟に見直しを実施します。
数値目標に関してはプロセスを評価しにくいので、行動や実績を日々記録して、期末誤差の防止につなげてください。
定期的な1on1ミーティング・面談の際には、評価の根拠となるような事実をメモに残すようにすると良いでしょう。
評価制度の運用で人事評価エラーを防ぐなら人事評価システム「P-TH/P-TH+」の活用を
人事評価は、社員のモチベーションや組織全体の成長に直結する重要な業務である一方、評価シートの集計ミスや期日遅れ、評価者間の基準のばらつきなど、運用上のエラーが起こりやすい領域でもあります。
こうした人的ミスを防ぐためには、紙やExcelに頼った属人的な管理から脱却し、システムによる一元管理と可視化を検討してみるのも良いでしょう。
そこで、おすすめするのが、「人事評価システムP-TH/P-TH+(ピース/ピースプラス)」。
「P-TH/P-TH+」とは、既存のExcel人事評価シートと、評価フローをそのままシステム化することができる人事評価システムです。
煩雑になりがちな評価シートのファイル管理が無くなり、人事評価の進捗状況もリアルタイムで確認することが可能です。
そして、メールの誤送信や評価シートの紛失、期日までの評価漏れといった運用ミスや情報の非対称性も防ぐことができます。
また、人事評価シートの内容も変更できるため、社員の増減や評価項目の変更があった場合でも反映することができます。
蓄積された人事評価データを分析することもできるので、人事評価制度や組織の定期的な見直し・改善にも役立ちます。
2025年4月から標準装備された『1on1機能』には、1on1ミーティングの記録を残せるテンプレートや、1on1ミーティングの実施時間や満足度を分析できる機能を搭載しています。
それにより、1on1の効果や効率を上げることが可能です。
1on1ミーティングを定期的、継続的に実施することが出来れば、人事評価面談もよりスムーズに実施することができます。
「P-TH/P-TH+」が人事評価全体の円滑な運用をサポートすることで、より丁寧に人事評価を行うことができるため、組織内で発生する人事評価エラーも防いでくれるでしょう。
まとめ
人事評価エラーは必ず起こるものと認識し、できるだけ人事評価エラーが起こらないような仕組み作りや対策を施すことが重要です。
不適切な人事評価は、社員一人ひとりのパフォーマンスやモチベーションの低下につながります。
結果的に、企業全体の生産効率の悪化をもたらしてしまうことにもなりかねません。
評価者は、日頃から公正な人事評価を心がけ、観察力や判断力、思考力などに代表される評価スキルの向上と、人事評価エラーの排除に努めるようにしましょう。
<< コラム監修 >>
株式会社サクセスボード 萱野 聡
日本通運株式会社、SAPジャパンで採用・教育を中心とした人事業務全般に幅広く従事。人事コンサルタントとして独立後、採用コンサルタント、研修講師、キャリア・アドバイザーとして活躍中。 米国CCE Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー、産業カウンセラー。
- カテゴリ:
- 人事評価
- キーワード:
- 人事評価






 << コラム監修 >>
<< コラム監修 >>