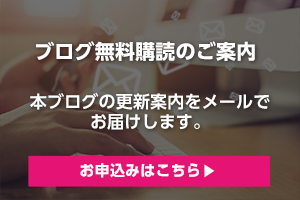近年、企業におけるハラスメント防止の取り組みが強化され、ハラスメントに対する認識が企業全体に浸透し、職場環境の健全化に大きく寄与してきました。
しかしその一方で、ハラスメントに対する過剰な反応や過度な配慮が、「ハラハラ(ハラスメントハラスメント)」を生み出してしまうケースも増えています。
そこで、こちらの記事では、ハラハラの意味や具体的な事例、職場に与える影響や企業がとるべき対策について解説します。
コンプライアンス遵守と円滑な職場運営の両立を実現するために、ハラハラに対する理解を深め、適切なマネジメントを行っていきましょう。
ハラハラ(ハラスメントハラスメント)とは?
ハラハラ(ハラスメントハラスメント)とは、本来であればハラスメントに該当しない正当な行為に対して「ハラスメントだ」と過剰に反応して、相手を困らせる嫌がらせ行為のこと。
ハラスメント防止への関心が高まる一方で、ハラスメントの被害を受けていない人が、上司や企業への反発の手段として“ハラスメント”という言葉を悪用するケースも増えてきました。
適切な業務指導や注意喚起を“ハラスメント”と主張されてしまうと、社内のコミュニケーションが萎縮してしまい、生産性や組織風土に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。
では、どうして「ハラハラ」が生まれてしまったのでしょうか。
ハラハラが生まれた背景と発生する要因について、くわしくお伝えしていきます。
ハラハラが生まれた背景と要因
昨今、パワハラやセクハラなどのハラスメントが問題視されてきたことで、国の法改正や企業のハラスメント防止対策が進んできました。
そして、メディア等で著名人や企業のハラスメント問題が報道されるようになったことで、個々のハラスメントに対する意識も以前と比べて高まっていきました。
ハラスメント防止に対する社会的な関心が高まり、ハラスメントを申告しやすい環境が整ったその一方で、ハラスメントを悪用した「ハラハラ」という新たな問題も生じてしまったのです。
また、「ハラスメントに対する従業員の理解不足」や「企業におけるハラスメントの定義不十分」も、ハラハラを助長させています。
『本人が不快に感じたらハラスメントである』など、定義や理解が曖昧のままだと、従業員によるハラハラに対して、会社や上司が的確に対応することができません。
また、ハラスメントの捉え方を逆手に取り、会社や上司に不満を持った従業員が嫌がらせのために、不当なハラスメントの訴えが横行するということも発生しています。
職場で起こるハラハラの具体例

ここからは、職場で起こる「ハラハラ」の具体的な事例やシーンについてご紹介します。
どういった行為がハラハラに該当するのか、ハラハラに対する理解を深めるためにも、一つずつ確認しましょう。
仕事の進捗確認
上司が単に仕事の進捗を確認したつもりでも、言い方やタイミングによっては部下が「非難されている」と受け取ってしまい、ハラハラが発生してしまうケースがあります。
たとえば、上司が部下へ投げかける「仕事は順調に進んでいる?」という言葉に対して、「仕事が遅いことを責められている」と感じてハラスメントだと訴える、といった事例です。
上司による仕事の進捗確認は、部下の業務を管理する上で当然の行為のため、部下の訴えはハラハラに該当します。
修正依頼やミスの指摘・注意
業務の精度を高めるための修正依頼やミスの指摘も、部下によっては嫌がらせやいじめと受け止める場合があります。
特に、人前で強い口調で注意されると、「自分を否定された」「いじめられた」と感じやすく、ハラスメントのように誤解されがちです。
本来は業務改善のための行為であっても、伝え方を誤ったり、部下が不快に感じたりすると、ハラハラに発展してしまいます。
能力に応じた仕事の振り分け
業務量や難易度を考慮して仕事を割り振るのは上司の役割の一つですが、部下によっては「自分だけに重い仕事を押し付けている」「長時間労働を強いている」と不満に感じることがあります。
逆に、「軽い仕事しか与えられず不当な扱いを受けている」とハラスメントを訴えるケースもあるので注意してください。
仕事の振り分けが「過大要求・過小要求」と受け取られ、ハラハラが発生してしまうことも少なくありませんが、振り分けの内容が妥当であればハラスメントには該当しません。
人事評価で低い評価をつける
人事評価で低い評価を受けた場合、部下の中には「わざと低評価を付けられた」「差別ではないか」と主張し、ハラスメントだと訴える事例があります。
成果やスキルに応じて公正に評価を下すことは上司の責務であり、人事評価の基準に基づき低評価をつけることは正当な行為です。
しかし、評価の根拠が不透明だと、本人の不信感は強まり、正当な評価さえも疑わしく感じてしまい、ハラスメントと訴えるケースがあるため、気をつける必要があります。
このようなハラハラを防ぐためには、評価基準とプロセスを記録、明確化できる人事評価システムの活用も有効です。
人事評価システム「P-TH/P-TH+(ピース/ピースプラス)」は、導入にあたって既存のExcel評価シートやフローを変更する必要が無いため、従業員への負担も少なくスムーズに導入することができます。
システムを通じて評価根拠を共有することで、評価の妥当性が客観的に示され、不当評価の疑念やハラスメント認定のリスク軽減につながるでしょう。
日常会話や雑談
職場で人間関係を築くために行った何気ない雑談や世間話も、「プライバシーの侵害だ」「セクハラだ」と主張して、ハラハラ行為をする従業員も少なくありません。
恋愛や家庭事情など、個人のプライベートに過度に立ち入ってしまうとセクハラ等のハラスメントに該当することもありますが、「今日のランチは何を食べたの?」といった会話は一般的には問題ありません。
ハラハラがもたらす職場への悪影響
では、ハラハラが横行するとどういった問題が生じてしまうのか。
こちらでは、ハラハラが職場にもたらす悪影響について、お伝えします。
業務の指導・指摘ができなくなる
ハラハラが職場に蔓延すると、上司がハラハラを恐れて、適切な業務の指導や、改善のための指摘ができなくなってしまいます。
「注意したらハラスメントと受け取られるのではないか」という不安から、誤った業務手順や非効率なやり方がそのまま放置され、結果的に組織全体の生産性が低下してしまう恐れがあります。
また、ハラハラを警戒して、部下との対話を避けて問題解決を先延ばしにしてしまうと、必要な教育がなされず、業務ノウハウも浸透しません。
ハラハラによって教える立場である上司の積極性が失われると、指導力も下がってしまい、部下が育たないという悪循環に陥ってしまいます。
部下に業務を依頼しづらくなる
「仕事量が増えたら不満に感じる部下が出てくるかもしれない」
「業務を依頼したら仕事を押し付けたと思われるかもしれない」
ハラハラを危惧するが故に、部下への仕事の振り分けや業務の依頼がしづらくなるという悪影響も出てしまいます。
業務上必要な仕事の割り振りが困難になると、上司が部下の仕事を肩代わりするということが発生し、組織マネジメントなど上司が本来成すべき業務が疎かになってしまう可能性があります。
業務運営が円滑に進まなくなり、結果的に、組織全体の生産性の低下につながります。
コミュニケーションが減ってしまう
職場でのコミュニケーションは、従業員の仕事へのモチベーションを上げたり、組織の連帯感を高めたりするのに必要不可欠です。
しかし、ハラハラが職場に広がっていくと、部下への声かけや、ちょっとした雑談さえもハラスメントにつながるかもしれないと懸念し、コミュニケーションを避ける上司が増えていきます。
職場でのコミュニケーションが萎縮し、話しづらい雰囲気が漂う環境では、業務に必要な情報共有や意見交換が滞り、ミスの増加や組織の一体感の低下へとつながります。
また、影響が長期に及ぶと、従業員同士の信頼関係が薄れ、職場の活気や生産性も損なわれてしまうでしょう。
ハラハラを防止するための3つの対策

ここからは、ハラハラを防止するためにできる対策について解説していきます。
以下の3つの対策を押さえて、ハラハラが発生しない職場づくりを目指してください。
ハラスメントの定義を明確にし、社内周知を徹底する
ハラハラ対策のために、まずは社内でハラスメントの定義を明確にし、ガイドラインを策定します。
「どこまでが業務上の適切な指導・指摘で、どこからがハラスメントか」など、判断基準を明文化することで、正当な指導を行いやすくなります。
また、ハラスメントを正しく従業員に理解してもらうために、社内研修を実施して、ハラスメントの定義や基準、具体例の周知を徹底するのが重要です。
ハラスメントに対する認識を社内全体で共有し、理解を深めることで、ハラハラの発生を防ぎ、ハラスメントの防止にもつながります。
ハラスメントの相談窓口を設置する
ハラハラを防止するために、社内では人事担当者やコンプライアンス担当者、外部では専門性の高い相談機関や弁護士など、社内外で複数のハラスメントの相談窓口を設けておくと有効です。
関係者が主観で「ハラスメントかハラハラか」を判断するのではなく、ハラスメントの知識を持った第三者の客観的な意見を求めることができるため、誰でも安心して相談できます。
また、ハラスメント情報の一早いキャッチアップができるとともに、ハラハラの問題が大きくなる前に対処できます。
ハラハラをする従業員への対応策を講じ、体制を整える
ハラハラが生じた場合を想定し、ハラハラをする従業員への対応策を講じ、体制を整えることも防止策の一つです。
ハラハラは、従来のハラスメント禁止規定に抵触します。
ハラハラも処罰の対象になってしまうという事実は、ハラハラの抑止力となります。
懲戒規定などに明記して、事前に従業員に周知しておきましょう。
また、ハラハラが発生した場合、対応マニュアルにしたがってハラハラの訴えを調査し、担当者が客観的にハラスメントの有無を判定することが大切です。
ハラハラの新たな発生防止につながるとともに、組織全体の健全な指導環境を守ることができます。
まとめ
ハラスメント防止対策が進む中で、「ハラハラ(ハラスメントハラスメント)」という新たな問題も浮上しています。
ハラハラを放置してしまうと、業務の指導や指摘ができず、職場内のコミュニケーションも減り、従業員同士の信頼関係が崩れるという、組織の生産性や人材育成に深刻な悪影響を及ぼします。
ハラハラを防止するために、指導とハラスメントの線引きを明確にし、社内周知を徹底し、個々のハラスメントに対する正しい理解を深めていくことからはじめていきましょう。
<< コラム監修 >>
株式会社サクセスボード 萱野 聡
日本通運株式会社、SAPジャパンで採用・教育を中心とした人事業務全般に幅広く従事。人事コンサルタントとして独立後、採用コンサルタント、研修講師、キャリア・アドバイザーとして活躍中。 米国CCE Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー、産業カウンセラー。
- カテゴリ:
- 人事部門向け
- キーワード:
- 人事評価







 << コラム監修 >>
<< コラム監修 >>