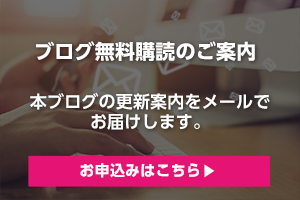現代社会において、従業員のメンタルヘルスは企業の生産性に深く関わっています。ストレスコーピングの必要性はますます高まっており、適切な対策を導入することは、離職率の低下や業務効率の改善につながります。また、組織全体のパフォーマンス向上にも大きく貢献すると言えるでしょう。本記事では、ストレスコーピングの基礎知識から具体的な実践方法、そして企業が取り組むべき支援策まで網羅的に解説します。ぜひ、ご活用ください。

ストレスコーピングとは?
「コーピング(coping)」とは「対処」「処理」を意味し、ストレスコーピングはストレスへの適切な対処法全般を指します。
心理学者R・S・ラザルスのストレス理論によると、ストレスの原因(ストレッサー)に対し、人はまずその有害性を判断する一次評価を行い、その後、どのように対処するかを考える二次評価を行うとされています。ストレスを軽減するためには、効果的な対処法を見つけることが重要です。
2022年の厚生労働省の調査では、82.2%の労働者が仕事に関するストレスを感じていると回答しました。過剰なストレスは生産性低下を招くため、企業にとって従業員の健康管理は重要です。適切なストレスコーピングにより、健康維持とパフォーマンス向上が期待できます。
参照元:厚生労働省「令和4年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況」
※P14をご参照ください。
ストレスコーピングの主な種類3つ
ここでは、代表的な3つのストレスコーピングの方法をご紹介します。
感情にアプローチする「情動焦点型」
情動焦点型コーピングは、ストレスに対して感情を調整する方法のことです。例えば、上司からの注意を冷静に受け入れ、前向きに捉え直すことがひとつの例です。また、ネガティブな感情を抑えるには、考えすぎず、気晴らしを取り入れるのも効果的です。気分が落ち込んだときには、友人に話したり、リラックスできる活動をしたりするとよいでしょう。デメリットとして、情動焦点型コーピングはスキルが必要なため、身につくまで効果を実感しづらいこともあります。
原因を取り除く「問題焦点型」
問題焦点型コーピングは、ストレスの原因に対処することで状況を改善する方法で、特に環境や人間関係の改善に焦点を当てるのが特徴です。このアプローチでは、ストレッサーそのものを根本的に変えることで、長期的なストレス軽減を目指します。具体的には、職場の人間関係を改善するよう努力したり、上司に配置転換を願い出たり、生活環境を見直したりすることが挙げられます。ただし、これらの対処法は実行が難しかったり、実行しても疲れ切ってしまったりすることがあります。思ったように問題が解決せず、かえってストレスが強くなることもあるかもしれません。
気晴らしをする「ストレス解消型」
ストレス解消型のコーピングは、ストレスを感じた際に気分をリセットするための手法です。例えば、趣味に没頭する、運動で体を動かす、好きな音楽を聞く、美味しい料理を味わう、ショッピングに出かける、温泉に行くといったものが挙げられます。これらは、心身をリフレッシュさせ、緊張をほぐす手段として多くの人に親しまれています。ストレス解消型のコーピングは、「気晴らし型」とも呼ばれ、短期間で気分転換できるのが特徴です。気分がリセットされることで、ストレスが軽減され、心の負担が和らぎます。
ただし、これらの方法はストレスの根本的な原因を解決するものではありません。特にストレス解消型のコーピングは一時的な発散に過ぎません。一方で、問題焦点型コーピングは根本的な解決を目指すものの、実行には時間と労力がかかるため、すぐに効果が出るとは限りません。状況に応じて適切な方法を選び、組み合わせて活用することが重要です。
ストレスコーピングのやり方
ここでは、自分だけで出来る実践的で簡単なコーピングを具体的に紹介します。日々の生活に役立てましょう。
コーピングリストを作成する
ストレスの軽減には、自分に適した対処法を持つことが重要です。その一環として、「コーピングリスト」を作成し、ストレスの種類と対処法をリストアップすると効果的です。
あれこれ頭で考えるだけでなく、リストを視覚化することで、ストレスを感じたときにすぐに実践しやすくなります。対処法は多いほど良く、自分が楽しく感じることや相談できる人などを思いつくままにたくさん書き出してください。例えば、おいしいコーヒーを飲む、好きな動画を見る、散歩するなどです。落ち込んでいるときではなく、元気なときにリストアップするほうが、色んなアイデアが浮かびやすいでしょう。
コーピングリストを作成した後は身近なところに置いておき、ストレスを感じたらどれかを選んで実践してみます。実践した方法について、効果の度合いを数値で表して(10点中○点など)メモしておくと、後で比較しやすくなるのでおすすめです。さまざまな方法を試すことで、ストレスに応じた適切な対処法を見つけやすくなるでしょう。
ストレスをモニタリングする
ストレスや漠然とした嫌悪感を覚えた際には、その度合いを5段階でモニタリングする方法もあります。客観的に記録することで、ストレスの強さや種類の変化を把握しやすくなります。
できるだけ客観的に、頭痛や腹痛、寝つきが悪い、食欲不振などの身体的症状や、イライラや憂うつ、自信喪失などの精神的反応を記録します。このモニタリングにより、ストレスを早期に察知し、優先的に対処すべきストレッサーを見極められるようになります。ストレスコーピングのスキル向上にも役立ちます。
企業にできるストレスコーピングの方法
ここでは、従業員支援の一環として企業ができるストレスコーピングの方法について解説します。
研修を実施する
企業が従業員のストレスコーピングをサポートするためには、研修の実施が効果的です。研修を通じて、従業員はストレスの原因を理解し、自分に合った対処法を学べます。例えば、新入社員向けにはセルフケアを重視したカリキュラム、管理職向けにはメンタルヘルス・マネジメントに焦点を当てたカリキュラムを実施するとよいでしょう。
また、ストレスマネジメントに関するセミナーやeラーニングの受講を推奨することで、従業員が自分に適したコーピングスキルの習得機会を提供することも重要です。特に、心理的負担の大きい業務に従事する従業員向けに、マインドフルネスや認知行動療法(CBT)を活用したプログラムを用意すると効果的です。こうした取り組みにより、従業員は日々のストレスに適切に対処する力を養うことができます。
メンター制度を導入する
従業員のストレス対策として効果的な方法のひとつに、メンター制度の導入があります。メンターとは助言者を意味します。企業においては、先輩社員がメンターとなり、若手社員(メンティー)に助言や支援を与えるのが一般的です。メンターのサポートを受けることで、メンティーはストレスを軽減しやすくなります。
評価を行う上司とは異なる立場のメンターがいることで、悩みを気軽に相談しやすくなります。先輩社員からの適切な助言は、効果的にストレスに対処するのに役立つでしょう。企業全体の健康管理にも貢献する制度です。
気軽に相談できる相談窓口の設置
従業員がストレスを抱えた際に、気軽に相談できる窓口を設置することも重要です。社内に専用の相談窓口を設けるほか、外部の専門機関と提携することで、従業員が安心して相談できる環境を整えられます。例えば、産業カウンセラーや臨床心理士によるカウンセリングを提供することで、メンタルヘルスの専門的なアドバイスを受けられるようになります。また、匿名で相談できるチャットや電話相談を導入すれば、対面では話しにくい悩みも気軽に相談できるでしょう。
1on1を実施する
1on1は、上司と部下が1対1で対話する貴重な機会です。この面談では、部下が抱える問題や課題を共有し、上司が相談しやすい環境を提供することで、ストレスを軽減できます。メンターとの面談や、評価を行う上司との面談など、形式は柔軟に対応できます。
重要なのは、上司が部下の話をよく聴き、気持ちに寄り添う姿勢を持つことです。1on1は、評価を目的とせず、相互理解を深め、部下の成長を促す場として機能します。話しやすい雰囲気を作るためには、言葉選びや前向きなフィードバックが重要です。
1on1をどんなふうに実施すべきか、さらに詳しい情報が知りたい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事:1on1ミーティングで話すこと|テーマの例やポイントを解説適切な人事評価も重要
公正ではない評価は、従業員にストレスを与える原因となることがあります。1on1の面談では、従業員が私生活を含む悩みやストレスについてメンターや上司に相談することがありますが、その内容が人事評価に影響しないよう配慮が必要です。評価制度の基準を明確にし、透明性を確保することで、従業員が「適切に評価されている」と安心できる環境を整えましょう。
人事評価の効率化には「P-TH / P-TH+」
人事評価システム「P-TH / P-TH+」は、今お使いのExcelの評価シートをそのままシステム化することが可能です。導入することで、時間のかかる集計作業を大幅に圧縮、進捗状況をリアルタイムで可視化することも可能になります。時間に追われて煩雑になりがちだった評価業務を、もっと丁寧に実施することができるでしょう。1on1ミーティングを実施する際にシステム内の評価データや社員情報を閲覧し、適切なフィードバックをするために活用することもできるでしょう。
オンプレミス版のP-THとクラウド版のP-TH+の2種類を提供しており、どんな企業にも柔軟に対応できます。
人事評価システム P-TH/P-TH+ | AJS ソリューション・サービスサイト Solution Navigatorまとめ
ストレスコーピングとは、ストレスに適切に対処するための方法や行動のことです。ストレスへの対処法をリストアップして実行するなど、個人で行える方法のほか、メンター制度や1on1など企業が主体となって実施する方法もあります。従業員個人の心身の健康を維持するだけでなく、企業の生産性向上にも深く関わるものなので、ぜひ実践していきましょう。
<< コラム監修 >>
株式会社サクセスボード 萱野 聡
日本通運株式会社、SAPジャパンで採用・教育を中心とした人事業務全般に幅広く従事。人事コンサルタントとして独立後、採用コンサルタント、研修講師、キャリア・アドバイザーとして活躍中。 米国CCE Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー、産業カウンセラー。
- カテゴリ:
- 人事部門向け





 << コラム監修 >>
<< コラム監修 >>