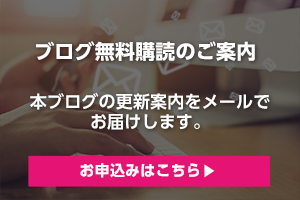人事評価制度の対象といえば、真っ先に想定されるのは正社員ではないでしょうか。しかし、アルバイト・パート向けに人事評価制度を整備することで、組織全体を活性化するさまざまなメリットが期待できます。そこで本記事では、アルバイト・パート向けに評価制度を導入するメリットをはじめ、評価制度の導入方法やそのポイントなどを解説します。

アルバイト・パートに評価制度を導入するメリット
アルバイト・パートに評価制度を導入することで得られるメリットとしては、
- モチベーションを高められる
- コミュニケーションの機会を増やせる
- 離職率を低下させられる
といったことがあります。ここでは、それぞれについて具体的に解説します。
モチベーションを高められる
評価制度の存在は、アルバイト・パートのモチベーション向上に大きく寄与するものです。評価基準を通して、「企業が自分に何を期待しているのか」を把握し、目標や努力の方向性を明確にして働きやすくなります。また、評価結果が昇給や待遇改善につながれば、「アルバイトでも成果を出せばきちんと評価してもらえる」という実感を得られるため、モチベーションをより一層高めることが可能です。
コミュニケーションの機会を増やせる
評価制度の導入には、コミュニケーションを活性化する効果もあります。業種によっては、シフトの兼ね合いなどが原因で、上司とアルバイト・パートとの対話が疎かになっていることも珍しくありません。
その点、評価制度の導入に伴って上司からのフィードバックの場を設けることは、コミュニケーションの機会を定期的に作る優れた方法です。上司からの丁寧なフィードバックは、「自分の何が評価されており、どこを改善すればよいのか」をアルバイト・パートが具体的に知り、上司や組織への信頼を深めるきっかけになります。
離職率を低下させられる
離職率の低下も期待できます。一般に、アルバイト・パートの離職率は、正社員に比べて高いことが知られています。例えば、厚生労働省の「令和5年雇用動向調査」によれば、令和5(2023)年におけるアルバイト・パートの離職率は23.8%で、正社員をはじめとする一般労働者の離職率の12.1%に比べて2倍近い結果になっています。
参照元:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」5,7ページ
アルバイト・パートの入れ替えが激しいと、採用・教育コストが高くなり、チームワークやサービス品質も悪くなりがちです。逆に言えば、評価制度の導入によって離職率が低下すれば、このような課題を一挙に改善できる可能性があります。実際、評価制度の導入によって、アルバイト・パートの離職率を低下させ、サービス品質の向上、さらには売上アップを実現した企業も存在します。
例えば、あるコンビニエンスストアでは、スタッフの勤務態度が悪く、離職率も高くて常に採用活動に追われていました。そこで人事評価制度を導入した結果、一人ひとりの長所や改善すべき点が明確化し、職場のコミュニケーションも活性化しました。スタッフのモチベーションが向上したことで顧客対応がより丁寧になり、サービスの質も改善されました。その結果、顧客満足度が向上し、売上アップにもつながりました。また、離職者が0人の状態でさらに新人を3人獲得し、人材の確保という問題も解消されました。
アルバイトの評価方法
アルバイト・パート向けの評価制度の導入・実施方法も、大まかな手順自体は正社員向けのものと変わりません。以下では、アルバイト・パート向けの評価制度の導入方法をステップごとに解説します。
1. 評価項目を洗い出す
最初のステップは、アルバイト・パートのどういった点を評価するのか洗い出すことです。ただし、評価項目の数が多すぎると運用が複雑になるため、10項目以内に絞り込むことをおすすめします。また、正社員とアルバイトでは業務の範囲や権限が異なることが多く、アルバイト同士でも、シフト(曜日・時間)によって業務内容が異なることは多々あります。評価項目を決める際はそうした違いも踏まえて、皆に共通する項目を評価の対象とするようにし、不公平にならないように留意するとよいでしょう。
2. 評価基準を定める
評価項目を洗い出した後は、評価基準を定めましょう。例えば、以下のような仕方です。
- よくできている=3点
- 普通=2点
- できていない=1点
理想としては、人事評価は誰が点数をつけても変わらないように、公平性を保つことが望まれます。そのためには、評価項目と評価基準の両方を、誰から見てもわかりやすい内容にする必要があります。また、評価項目と同じく、業務範囲や勤務時間の違いなど、本人の努力や能力、成果とは関係ない部分で評価に差が出ないように注意しましょう。
3. 評価シートを作成する
評価項目と基準が定まったら、次は評価シートの作成です。評価シートには、評価対象の期間や従業員情報などの記載項目を含めると、管理しやすくなります。評価シートの作成に関しては、Web上などにあるテンプレートを利用すると便利です。ただし、評価項目などに関しては、自社のアルバイト・パート向けに調整するようにしましょう。
アンカーテキスト:人事評価における能力評価シートとは? 社内での活用方法や運用のポイント
4. 評価して結果をフィードバックする
評価シートが完成したら、実際に評価制度の運用を開始し、その結果を面談などでアルバイト・パート本人にフィードバックします。良かった点と改善すべき点を具体的に伝え、成長を促しましょう。
評価を伝える際は、良い点も悪い点も、できるだけ具体的に示すと効果的です。たとえば、単に「接客態度が良い」と言われるよりは、「いつも笑顔で、誰よりも先にお客様へ挨拶している」などと評価された方が、従業員は自分の長所を正確に把握し、上司がしっかり自分を見守っていると感じやすくなります。また、一方的に上司が発言するだけでなく、従業員側の意見や悩みなどを聞く時間を設けることも大切です。
アンカーテキスト:人事評価のフィードバック面談はどのように行う?ポイント、注意点を解説
アルバイト・パートの評価でのポイント
アルバイト・パート向けの評価制度を効果的に運用するためには、基準の明確化とその周知、公平性の確保などが成功の鍵になります。
評価基準を明確にして周知する
これは正社員にも当てはまることですが、評価基準は誤解や曖昧さがないように明確に設定しましょう。そのためには、「担当業務のミスの少なさ」など、できるだけわかりやすく、定量的に把握しやすい指標を設定するのがコツです。また、「接客」のように一見抽象的な評価項目に関しても、「挨拶」や「接客の丁寧さ」など、どのような要素を評価するのか明確に示すことで客観性を確保しやすくなります。
さらに、制度の透明性を高めるために、評価基準を従業員全体へ周知することも欠かせません。アルバイト・パートは、正社員よりも研修が少なく、制度への理解が浅くなりやすいので、働き始めの段階からしっかり制度の概要や評価基準について説明しておくことが大切です。これらの点に留意することで、評価に対する従業員の納得感を強め、仕事へのモチベーションを向上させやすくなります。
公平に評価する
人事評価は公平に行うのが原則です。アルバイト・パートは正社員に比べて離職のハードルが低いため、「若いから」「女性/男性だから」などの公平さを欠く理由で評価が低いと、「どうせ頑張っても評価されない」と早々に離職してしまう恐れがあります。スキルや貢献度など、なるべく客観的かつ可視化しやすい要素を評価基準にするのがポイントです。
ただし、公平に評価するといっても、すべてのアルバイト・パートを一律の基準で評価するのは適切ではありません。例えば、週5のアルバイトが10の成果を、週2のアルバイトが5の成果を出したとしましょう。この場合、勤務時間の違いを考慮せずに単純な成果量だけで両者を比べると、より優れた生産性を発揮している後者の評価が不当に低くなってしまいます。それぞれの雇用形態や働き方の違いも踏まえた上で、公平に評価できるように基準を決めましょう。
効率的に管理することも重要
アルバイト・パートにも評価制度を適用することで、従来よりも評価・管理作業の手間が大きくなることが想定されます。過度の負担が生じた結果、本来の業務に支障をきたしたり、評価作業がいい加減になったりしては意味がありません。こうした課題を防ぐためには、以下の部分で紹介するようなシステムの活用によって、人事評価業務を効率化することも検討の価値があります。
アルバイト・パートの人事評価においても「P-TH / P-TH+」
アルバイト・パートの人事評価を効率化するには、人事評価システム「P-TH / P-TH+」の導入がおすすめです。「P-TH / P-TH+」はあらゆる企業の人事評価制度に対応可能で、モバイル端末でも簡単に入力できます。評価シートの内容も柔軟に変更できるので、正社員向けの評価シートをアルバイト・パート向けに作り直すことも簡単です。蓄積された評価データを分析することもできるので、評価制度をスムーズに人材育成へ結び付けられます。
関連記事:人事評価システム P-TH/P-TH+ | AJS ソリューション・サービスサイト Solution Navigator
まとめ
アルバイト・パート向けにも人事評価制度を導入することで、モチベーションの向上や離職率の低下など、多くのメリットが得られます。制度を導入する際は、明確な評価基準を設定し、公平性や透明性を保ちながら管理運用することが大切です。ただし、評価対象が増える分、管理運用の手間が増えることが予想されます。こうした課題に対応するには、評価システム「P-TH / P-TH+」などのシステム活用を通して、評価業務の効率化を図るのがおすすめです。
<< コラム監修 >>
株式会社サクセスボード 萱野 聡
日本通運株式会社、SAPジャパンで採用・教育を中心とした人事業務全般に幅広く従事。人事コンサルタントとして独立後、採用コンサルタント、研修講師、キャリア・アドバイザーとして活躍中。 米国CCE Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー、産業カウンセラー。
- カテゴリ:
- 人事評価





 << コラム監修 >>
<< コラム監修 >>