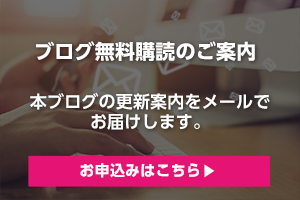人事評価は、職員の不満につながることも多いものです。基準が曖昧だったり、わかりやすい制度・システムがそもそも構築されていなかったりなど、人事評価における課題が山積みである施設も多いでしょう。
そこで今回は、社会福祉法人が人事評価制度を作るにあたってチェックしておきたい手順や方法とともに、現状多くの施設が直面している人事評価の課題やトラブルについて解説していきます。
社会福祉法人に人事評価制度改革が求められる背景とは
人事評価制度に関する課題や、現場で働く人たちの不満は、どのような組織においても生まれるものです。それは社会福祉法人も例外ではありません。近年は社会福祉法人の人事評価制度の導入・改善・見直しが業界では大きな課題となっています。
まずは、なぜ社会福祉法人にも人事評価制度が必要とされるのかを整理していきます。
根本的な考え方は通常の企業と同様です。企業はよりよい製品やサービスを提供し業績を向上させることが大切です。そのためには従業員一人ひとりのモチベーションの向上が欠かせません。それぞれを公正に評価することはモチベーションの向上にも直結します。
社会福祉法人は、営利目的ではないとはいえ、よりよいサービスを実施し続けていくためにも職員の評価が重要になってきます。一人ひとりの能力や業務量などを公正にチェックし、評価を決めることは、業務の効率化やサービスの質の向上、そしてやはり職員のモチベーション管理につながっていくのです。
社会福祉法人の人事評価制度の課題とは
続いて、社会福祉法人の人事評価には具体的にどのような課題やトラブルがあるのかを整理していきます。評価に対する不満やそれに伴うトラブルが生まれることは、放置すると大きなリスクになりえます。まずは課題を紐解いていきましょう。
評価基準が曖昧になっている、公平・公正な評価が行われていない
人事評価における課題の一つとして、評価基準に具体的な取り決めやルールがないことはよく取りざたされることです。基準が曖昧な状態だと、評価を決定する人の考え方や独自のルールに依存してしまうことが多く、公正な評価を得られなくなることは少なくありません。人事評価は、公平かつ公正なものであって然るべきです。しかし、それは簡単なことではありません。
施設におけるポジションや担当している仕事、資格などを総合的に見たうえでの統一された基準に基づく評価になっていないと、職員の不満を生みやすく、業務効率や職員のモチベーションに関して悪い影響を及ぼすことになるのは明らかでしょう。
「これだけ毎日残業しているのに給料はいつまでも低い」「上司と関係が悪いせいで評価に偏りが出ている気がする」などの不満も生まれてくるでしょう。
「誰が見てもわかりやすい評価ルールや基準」が設けられていないと、結果として本人も何を頑張れば評価されるのか把握できず、モチベーション低下につながります。
育成する仕組みができていない
福祉の仕事の現場では、研修やOJTなど充実している場合もありますが、職員一人ひとりに目を向けた育成プログラムや研修制度などについてはしっかりと整備されていないことも珍しくありません。昇格のために必要とされる能力や条件などが明確に決まっていないなど、曖昧な仕組みになってしまっていることも多く、さらには日々同じ仕事の繰り返しでモチベーションを自分自身でコントロールすることが難しい、という話も耳にします。
評価基準や研修体系を明らかにしたうえで、職員一人ひとりが公平にキャリアを積んでいけるように環境を整えることが、社会福祉法人を含む組織には求められています。
社会福祉法人の人事評価制度構築の手順
人事評価制度を明確に定めていない社会福祉法人は、職員のモチベーションダウンによる業務効率の低下、退職者の増加などさまざまな問題に悩むことになります。そういった課題を抱える社会福祉法人にとって人事評価制度構築は急務と言えるでしょう。以下から、制度を整えるための手順を解説していきます。
職種別で等級に応じた職能要件を作成
最初に意識したいポイントとして、職種ごとに等級に応じた職能要件を取りまとめる必要があります。それぞれの福祉施設、そして役職によって、必須となる職能要件は異なりますが、職員を公正に評価していくためにはこれらを見直し、明確にすることが重要となります。
具体的な職能要件については、厚生労働省の発表している定義を活用することができます。職種それぞれのフォーマットが用意されており、それらを参考にすれば早期に対応することが可能となるでしょう。
行動基準の整備
職員一人ひとりの能力や適性の程度は、具体的な基準のもと評価されるようになっていることが望ましいです。理由としては行動基準がわからない場合、どのような行動を目標・理想として業務に従事していけばよいのか、職員が明確な行動を起こせないからです。
そのため職能要件を作成することに伴って、行動基準も明らかにしましょう。基準を職員が明確に把握することで、評価する側もされる側も基準を基に行動でき、公平かつ公正な評価につなげることができます。
評価制度の整備
職能要件と行動基準を明らかにしたら、続いて評価制度をまとめることにつなげていきます。どのように日々の業務の頑張りが評価に反映され、どのようにキャリアを積んでいくことができるのか、できるだけわかりやすいシステムにしましょう。
まず導入したいのは目標管理制度です。略してMBOと呼ばれる目標管理制度とは、「定めた目標に対してどれくらい達成できたか」というポイントに焦点を当てて、職員を評価していく考え方です。
まずはそれぞれの課題に合わせた目標が必要です。
そのため目標を職員それぞれが自分で設定し、評価者はその目標達成率を定期的にチェックしていきます。その中で都度、修正や見直しにつなげていくことができます。目標管理制度は目標を自分で設定し、達成の度合いをチェックするからこそ、評価に反映しやすいのが大きな利点です。
ただ、制度導入を図るのみでは、実際にその制度をうまく運用していくことは難しいのも事実です。
そのため制度を構築した後は、職員一人ひとりが適切にPDCAサイクルを回していけるよう注力することが大切です。そのうえで公正な評価が実施されるように、評価者に対しても積極的な研修やトレーニングなどを行っていくことも必要になってくるでしょう。
制度作りと実際の環境整備の両方のポイントをおろそかにしないことが、人事評価の満足度を上げることにつながります。
まとめ
社会福祉法人も一般企業と同じく、品質の高いサービスを継続していくためには、職員を公正に評価していくことが必要不可欠となるでしょう。曖昧な評価基準や制度は、職員のモチベーションに悪影響をもたらします。
AJS株式会社では、あらゆる業界で活用可能な人事評価システム「P-TH/P-TH+」を提供しています。社会福祉法人は人事評価制度の構築に悩むことも多い業界と言えますので、明確な制度を作るためにシステムの導入も効果的です。人事評価制度の運用にお悩みの際には、AJS株式会社へぜひご相談ください。
- カテゴリ:
- 人事評価
- キーワード:
- 福祉