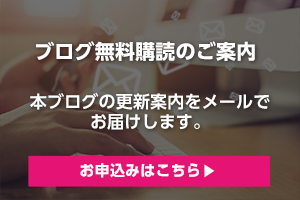近年、「ディーセントワーク」という言葉が注目されています。職場環境などに関連する言葉ですが、これがいったいどのような概念なのか気になる人事担当の方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、ディーセントワークの概念やメリット、また導入のポイントについて詳しく解説していきます。
ディーセントワークとは
ディーセントワーク(Decent Work)とは、日本では「働きがいのある人間らしい仕事」と定義されています。これは1999年に開催された国際労働機関総会において、事務局長によって初めて使われた言葉です。そのため言葉自体それほど新しいものではありません。しかし近年の労働環境や社会情勢の変化、SDGsの採択などによって注目を集めています。
なお国際労働機関総会において当初は、「必要な技能の習得と賃金で暮らしていけるように国・企業が支援すること」や「社会保障の充実による健康的な職場環境の保障」、「職場での問題が平和的に解決できるよう社会対話を推進」「労働者の権利保障・尊重」という4つの取り組みが重要な要素として掲げられていました。
そして、日本の厚生労働省においては以下の4つがディーセントワーク実現のために重要であると考えられています。
- 働く機会が与えられ、生計に足る収入が得られること
- 労働者の権利が保障され、職場での発言が認められること
- プライベートと職業生活の両立ができ、安全な職場環境に加え雇用保険・医療などの制度が確保されること
- 平等な扱いを受けること
それぞれに表現は少し異なりますが、いずれも誰もが仕事と家庭との両立を可能とするような環境整備をし、人間らしい仕事を皆が持てる社会となることを目指す、ということです。そのためにも、労働者が個別に抱える育児・介護といった事情も考慮されなければなりません。また、そのような事情があっても問題なく働けるよう社会保障を充実させることが大事です。企業の努力のみならず国も一体となって取り組むことが欠かせません。ディーセントワークではこのような理想的な環境を実現するために作られた言葉なのです。
SDGs達成の一環としても注目される
SDGsとは2015年の国連サミットにて採択されたもので、2030年までに達成すべき目標、その達成のための具体的な取り組み内容等から構成されています。目標の中には、例えば貧困をなくすことや飢餓をなくすこと、全ての人に健康と福祉を提供することや、質の高い教育を提供すること、ジェンダー平等などが掲げられています。
そして労働に関しても目標が定められています。持続的な経済成長や生産的完全雇用、およびディーセントワークの推進が条文に組み入れられており、ディーセントワークとSDGsの目標が一致していることから、ディーセントワークはSDGs達成のために欠かせない存在です。
この達成のために取り組むのは日本だけではありません。そのため各国はそれぞれに直面している課題解決に向けて施策を講じていく必要があります。日本では長時間労働の問題が深刻化しているため、特にこの点への取り組みは積極的に行われています。
ディーセントワークのメリット
ディーセントワークが実現されることで、労働者と企業の双方に様々なメリットが生じます。
取り組み始めはコストや労力が問題になるかもしれませんが、長期的な視点を持って企業も積極的に環境改善に取り組むことで、満足度向上や利益拡大が望めます。具体的には以下のようなメリットです。
従業員満足度の向上
第一に、従業員の負担が軽減されます。ここでの負担は、勤務中におけるもののみならず、生活全般を考慮した負担のことを意味します。なぜならディーセントワークでは、生産性向上や業務効率改善など企業の利益を重視するのではなく、従業員視点での働きやすさに着目するからです。
その実現を目指す過程では業務効率のアップが必要になるなど、副次的なメリットが得られる可能性はありますが、あくまで従業員にとっての環境改善が重要です。
そこで、例えば短時間勤務や週休3日などの導入、その他多様な働き方を提供するなどの手段が考えられます。それにより従業員それぞれのライフスタイルに対応できるようになり、結果として従業員満足度の向上が期待されます。満足度が上がれば人材の流出を防止でき品質低下も防ぎやすくなるなど、企業の利益としても還元されるでしょう。
企業の社会的イメージの向上
従業員に優しい環境を整備すれば、世間からの評判も良くなります。企業の持つ社会的イメージが向上すれば、取引先や消費者からも信頼を得やすくなり、契約を成立させやすくなったり、売上向上に繋がったりもするでしょう。
逆に、世界中の多くの企業が環境改善に取り組む中長時間労働やハラスメント問題を是正しないでいると、企業の信頼も失墜してしまいかねません。
SNSも普及する現代においては、個人の発信が社会全体に響き渡ることも珍しくありません。悪評が拡散され、持続的な経営に甚大な影響を及ぼすおそれもあります。
人手不足の解消
今後の日本は、長期に渡って人手不足に悩むことが予想されています。そこで従来の働き方しか採用できなければ、新たな人材を確保することはできず、企業活動を続けられなくなることも起こり得ます。
そこで、育児や介護のためフルタイムで働くことが難しいという方でも働けるように整備することが、より重要になってくるでしょう。妊娠・出産による負担を負う方へのフォローなども重要です。
また、これらの取り組みは単に人材確保の窓口を広げることのみならず、優秀な人材の獲得にも繋がるというメリットを持ちます。多様なニーズに応える制度が整っていることで企業の評価が高まり、優秀な人材も集まってくるからです。
ディーセントワーク導入時のポイント
ディーセントワークを導入する上で気をつけたいことはいろいろありますが、ここでは厚生労働省で推奨されているポイントを紹介しておきます。主に以下の7つを軸に考えることが推奨されています。
- WLB軸(仕事と生活のバランスを取りながら、いつまでも働き続けられる職場か)
- 公正平等軸(あらゆる労働者が平等に活躍できる職場か)
- 自己鍛錬軸(自分のスキル・技能を鍛錬できるか)
- 収入軸(持続可能な生計に足る収入を得られるか)
- 労働者の権利軸(労働三権など権利が確保されているか)
- 安全衛生軸(安全な職場環境が確保されているか)
- セーフティネット軸(雇用保険や医療・年金制度など最低限保障制度に加入している職場か)
これらの軸を念頭に、まずは自社の評価をしてみるのがおすすめです。どの軸において低水準となっているのか把握し、注力すべきポイントが見つかれば具体的な施策を検討していくと良いでしょう。
人事担当者のディーセントワーク実現の為に
さて、ここまでディーセントワークについてお話して参りましたが、私たちAJSは人事担当の皆様ご自身の労働環境改善に少しでも貢献できればと、人事評価システムを開発しています。
人事評価の多くは、エクセルを活用している企業様が多くございますが、その入力依頼、回収、未提出者の追跡、集計、レポートなど、その手間は膨大ですが、必要不可欠で、人事担当者の皆様を悩ませている事をよく知っています。
私たちが開発をした人事評価システム「P-TH」は、その手間を大幅に削減し、人事担当の皆様のディーセントワーク実現に一歩も二歩も進んでいただけるはずです。資料をご用意致しておりますので、是非ご覧になってみてください。
まとめ
ディーセントワークは、ハンディキャップを持つ人など、あらゆる個人の活躍を支援する考え方に基づきます。個人的に抱える問題にも対応できる環境構築は企業にとって欠かせないでしょう。離職率を減らす一助ともなり、企業イメージの向上などのメリットもあります。多様な働き方ができる制度を設け、公正な人事評価を行うことで従業員の満足度を高めることが大切です。
- カテゴリ:
- 人財活用
- キーワード:
- 人財活用