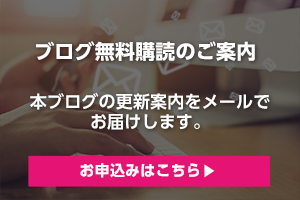人事評価制度を構築し社内で定着させるためには、関係各所からメンバーを招集し、プロジェクトチームを組んで取り組む必要があります。この記事では、人事評価制度を定着させるために、導入開始までのマイルストーン設定とスケジュール設定の手順を解説していきます。
人事評価制度導入開始までのマイルストーン
人事評価制度の新たな導入においては、通常の業務の一環として行われるべきものではありません。しっかりとプロジェクトを組み、腰を据えて取り組むのが一般的です。またプロジェクトは、ステップを決めて実行する必要があります。
では具体的に、どのような順序で進めていけばよいでしょうか。まずは導入開始までのマイルストーンを解説します。
人事制度のスコープを決める
人事制度の目的は従業員の評価を公正に行い、その処遇と位置づけを適切に判断することです。そうした人事制度を作る際は、まず制度に何をどこまで含めるかというおおよその範囲(スコープ)を決定します。
人事制度の中身として、まず思い浮かべるのは等級制度・評価制度・報酬制度の3つです。ただし広義には、教育・能力開発や福利厚生、出張、転勤、採用なども人事制度に含まれるため、それらをスコープに網羅して検討する必要があります。
人事制度においては基本となる等級制度・評価制度をベースとして、従業員教育を効果的に連動させつつ、個々人のキャリアアップがスムーズに進むように設計しなくてはなりません。その上で環境変化や技術革新によって求められるスキルが変化していく中、どの従業員がどういったスキルを保有しているか把握しやすいデータベースの構築も検討する必要があります。
終身雇用が崩壊しつつある現代においては、成果主義を取り入れる企業が増えてきています。また、ビジネスニーズの移り変わりによって企業ビジョンや経営方針も変化する可能性があります。そのため、人物像や等級ごとに必要なスキルについても、柔軟に軌道修正がしやすいようなスコープにしておく必要があるかもしれません。
プロジェクトメンバーを決める
スコープが決定したら、次に決めるのはプロジェクトのメンバーを誰にするかです。中心となるのは当然人事部ですが、従業員教育を行う教育部門、データベースの管理・運用を行う社内システム部門の担当者、現場を熟知した各部門・各職種の担当者にも、不足なくプロジェクトに加わってもらう必要があります。なかでも自部門・自職種に関する知識だけでなく、他部門・他職種の重要性を把握している人材を選びたいところです。さらに中小企業では、プロジェクトの責任者として社長を含む経営陣にも関わってもらわなくてはいけない場合もあるでしょう。
制度構築のスケジュールを決める
メンバーの次に決めるのは、人事評価制度を構築するためのスケジュールです。スケジュールを大まかにわけると、職種や賃金等の状況を把握する「現状分析」、人事評価制度の大枠を決定する「概要設計」、その概要を基に細かい項目を詰めていく「詳細設計」、最後に導入を開始するための「導入準備」となります。
なお人事評価制度を含め、システム導入においては設計のどこに不備があるかを導入前に全てあぶりだすのが困難です。人事評価においては、さまざまな立場の人がそれぞれの視点で判断を行います。そのため、導入時点でそれらすべてのケースを割り出して不備がないか検討するのは現実的ではありません。
それを踏まえ、できるだけ導入後の不備発覚によって大きな問題が発生しないようあらかじめ準備しておく必要があります。具体的には導入準備の段階において社内告知を周知徹底し、なるべく速やかに、なおかつ的確に不備を発見できるようにしておきます。
人事評価制度導入のスケジュール
人事評価制度は、具体的にどのような流れで構築を進めていけばよいでしょうか。ここでは、人事評価制度を構築する際のスケジュールについて解説します。
1: 現状分析
まずは現在運用している人事評価制度の内容確認と、運用状況の分析を行います。人事評価制度は多くの人によって運用されることから、それぞれの立場により異なる問題意識を抱えている可能性があります。それらを出来る限り漏れなく集めるために、従業員や経営陣に対するインタビューやアンケートなども必要でしょう。
その上で現在の経営の方向性も踏まえ、現行の人事制度の問題点がどこにあるか分析します。まだ人事評価制度が存在していない場合は、従業員・経営陣のインタビュー・アンケートの結果から、分析によって現在抱えている組織の課題は何かを探ります。
2:概要設計
現状分析が終わったら、その内容をもとに人事評価制度の作成を進めていきます。経営方針・経営理念をふまえて、どのような人事評価制度を作っていくかコンセプトを決定していきます。どのような人材を求めどんな組織を作っていくかのイメージを明確化し、等級や評価などの諸制度の基本的な要件を決めていきます。
3:詳細設計
前のフェーズまでに決められた基本要件にもとづき、人事評価制度の詳細を詰めていきます。各等級の基準や昇格・降格の要件を整備したり、評価基準を決定したりするのもこのフェーズです。その他、人事各制度で利用するツール類の作成、運用ルールの整備等も行います。
その際、決定した制度を基にしてシミュレーションを実施し、従業員ごとの給与の変動や人件費の総額がどのように変化していくか、さらに従業員ごとの評価の差がどのように生じるかなどを推測します。それらの結果をもとに、さらに各制度の詳細をチェック・改修をすすめていきます。
4:導入準備
詳細設計まで終了したら、導入準備に入ります。いくらクオリティの高い人事評価制度が完成しても、従業員に理解されなくては意味がありません。
ガイドブックや説明資料の作成、説明会やトレーニングなどを実施し、全員に新制度の理解を促します。目標管理制度を採用するのであれば、従業員が個々の目標を設定するためのトレーニングも必要です。
また評価者となる管理者についても、評価や採点の結果が評価者間でぶれないように研修等で意識合わせをしておきます。このフェーズを怠ると評価の公正さが失われてしまい、従業員に不満を持たれたり信頼感が失われたりするおそれがあります。
まとめ
人事評価制度を構築・定着させるためには、まず人事制度のスコープとプロジェクトメンバーを選定し、その上で制度を構築するまでのスケジュールを決めます。次に制度の構築にあたっては現状分析から入り、大まかな構築方針を決定した上で、制度の詳細を設計します。最後にガイドブックの作成やトレーニング等を行って社内に対して制度の内容を十分に周知することが必要です。
<< コラム監修 >>
株式会社サクセスボード 萱野 聡
日本通運株式会社、SAPジャパンで採用・教育を中心とした人事業務全般に幅広く従事。人事コンサルタントとして独立後、採用コンサルタント、研修講師、キャリア・アドバイザーとして活躍中。 米国CCE Inc.認定GCDF-Japanキャリアカウンセラー、産業カウンセラー。
- カテゴリ:
- 人事評価
- キーワード:
- 業務効率化






 << コラム監修 >>
<< コラム監修 >>